
白田の情報法研究報告

 はじめに
はじめに

|
何をしているのか、よくわからないといわれたりする私の研究について、広く皆さんに知って頂くために、研究している内容をリアルタイムに提供することを目的としてここを開設しました。 相変わらずコピーライトの史的展開の方の直接販売受け付けてますので、よろしく(^^)/。 講義要項、講義資料、履修登録等など、講義に関することについては、下の小さなバナーをクリックしてください。

|
|
さて、葉月。夏休みです。8月の第一週は合宿と避暑にあてました。演習 I と演習 II の合同合宿を富士吉田で、つづいて避暑を小淵沢で、そのあと付き合いのある会社の全体ミーティングを清里で行ったわけです。これでおおよそ一週間の旅行となりました。白田ゼミの合宿の様子については、私からの報告がこちらに掲載されています。学生さんたちからも報告が出るんだろうと期待してますが、でるのやら、どうやら。 富士吉田での学生さんとの合宿を終え、電車に乗って大月経由で小淵沢に向かいます。その車内で読んだのが長澤忠徳 著 「インタンジブル・イラ」 サイマル出版会。 私たちが「デザイン」というとき、職人的な手仕事、やたら高尚だが意味不明の評論というようなものを思い浮かべがちです。ところが、同書を読むとこの見方を変えさせられます。物事に一定の形、配置を与えるという作業は、すべての学問分野において抽象的には行われている作業であるわけですが、この抽象的な把握能力、整理能力を「デザイン」と置き直しているわけです。自分の法律学という仕事と思い合わせても納得する部分多数でして、もしかするとデザイン能力は基礎学力の一種なのかもしれないなぁ、と考えました。 しかし、美術大学の先生がこういう社会の全体スキーマについて考察しているなんて、ぜんぜん知りませんでした。自分の不勉強を恥じます。 3年連続でお世話になっているペンション・ウォーミングアップに到着。ここでただひたすら本を読むという正しい意味での避暑にはいります。この宿のいいところは、食事がよいことと、緑陰涼やかで広いしっかりとしたテラスがあるところです。右の写真は朝の庭、左下の写真はそのテラスです。
|

|
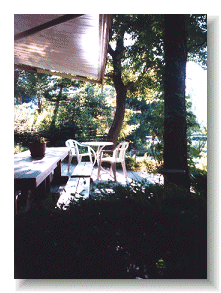
|
ここで「インタンジブル・イラ」を読了しまして、続いて Bill Readings著、青木健 / 斎藤信平 訳 「廃虚のなかの大学」法政大学出版会に着手。著作権の歴史研究をやっていた関係で、本を頂くようになった成城大学の青木先生から、今年も7月に翻訳書をおくっていただきました。毎年ハードカバーの翻訳書を出されるのですから、精力的なお仕事ぶりに感服せざる得ません。それにひきかえ、自分の仕事が遅々として進まないのがなんとも悲しいですね(泣)。え、「遊んでるからだろ」って? まあまあ、それはそれとして。 昨年読んだ「文筆業の文化史」の方は、研究分野に関係していたのでサクサク読めたのですが、この「廃虚のなかの大学」は、哲学・思想・社会学系に分類されるもので、私には馴染みのない用語や概念が多数。なんとも読みすすめるのに難儀しました。 同書で、大学が国民国家における国民文化の生産・伝達機関として国家システムのなかに位置づけられていたというようなことを今更ながらに知りました。「まあ、そうだろうなぁ」と思うわけです。で、その国民国家だの、国民文化だのが、国際化やら情報化やらで崩壊してしまえば、「何のために大学あるのよ」ってことになるわけで、そこを模索しているのが現代の大学の実状らしいです。職業学校化するというのも十分意味のある選択肢だと思うのですが。
|
|
今後の大学の在り方は、要するに国民国家概念から独立した「文化」なるものを発見あるいは抽出し、次世代に伝達することがその目標となるのだろうかと思います。ところが、まず、何が「文化」かという部分で論争があり、また「文化」なる価値が非常に漠としていることから、やたらと「文化」を振りかざすことは教育機関としての大学に堕落の免罪符を与えてしまう危険すらあるわけです。 まあ、そのあたりの難しい話に首を突っ込んでも、太刀打ちするだけの背景知識がないのでこのへんで切り上げます。 で、我が身を反省してみるわけですが、私のやってる音楽やら、電子工作やら、小説かきの真似事、絵などの「遊び」についていえば、いずれも「文化」やら「教養」に該当するわけで、「そんならオッケー♪」と正当化してしまうことも可能なわけですが、それだけじゃマズいことは明らか。大学の先生もちゃんと授業料分以上の教育を提供しないとね。提供できてるかな?うーむ。
|

|
|
とはいえ、ゼミ合宿の様子を思い起こすと、上記の意味での「遊び」を学生さんたちに提供することが、今もっとも必要とされている大学の機能なのかもねぇ、と考えたりもするわけです。一般的な学生さんたちの「遊び」ってどうも貧困なような気がするのですよ。酒かっくらって騒いでりゃ幸せ♪ってんじゃなんか淋しくないですか? そんなこんなことを考えつつ、京都の古本屋で買ったHelmut Presser著、轡田収 訳 「書物の本」 法政大学出版会 に着手。こちらは、私の専門分野に関連した本ですので、楽に読み進められます。翻訳書ですしね。内容は完全に書物の歴史に関する本で、それぞれのトピックは興味深く面白いのですが、私の研究に貢献するような内容はあまり見つかりませんでした。非常に面白いのだが「何のやくにたつの?」って聞かれてもよくわからない。これが文化というものなんでしょうか。 その後、清里の清泉寮に移動。この清泉寮というところは、私にとって驚きの宿だったわけですが、そのあたりの詳しい話は、またいつか。 | |

 注意
注意

|
ここに掲載されている文書の内容は「無保証」 です。従って、ここに掲載されている文書は「見本」であると御理解ください。また、御意見・御批判は歓迎しますが、それらは必ず「完全版」について行って下さい。完全版はポストスクリプトファイル 、DVIファイル、またはPDFファイルで提供します。ポストスクリプトやDVIファイルが必要な方は私にお手紙ください。個別にファイルをさし上げます。 エキスパンドブックやPDF等の電子テキスト一般の読み方についての解説については、 こちらをご覧ください。 latex2htmlがうまく使えなかったので、自前のコンバータを作って LaTeXの原稿からHTMLファイルを作成しています。このため、LaTeXで使用される記述法を完全にHTMLに置き代えられていないので、時々、意味不明の記号が残っていたりします。
|

 履歴書 履歴書
| |
 小論集 小論集
| |
 情報法の背景, 2000年5月12日 一橋大学 法文化構造論にて報告 情報法の背景, 2000年5月12日 一橋大学 法文化構造論にて報告
| |
 著作権の情報流通技術決定論 仮説, 2000年3月18日 国際日本文化研究センターにて報告 著作権の情報流通技術決定論 仮説, 2000年3月18日 国際日本文化研究センターにて報告
| |
 倫理問題, in bit別冊「情報セキュリティ」, 共立出版, 2000年1月 倫理問題, in bit別冊「情報セキュリティ」, 共立出版, 2000年1月
この「倫理問題」の原稿は、下の「コンピュータ・ネットワークにおける自由と倫理」で用いた論文に加筆したものです。重要な部分について加筆したので、ご批判は書籍に掲載されたものに対して行ってください。明大情報科学センター紀要には、私の口述内容が掲載されておりまして、論文は掲載されませんでした。 | |
 もう一つのプライバシーの話 --- 中学生、高校生のためのプライバシー問題へのヒント ---, 青空文庫, 1999年9月 もう一つのプライバシーの話 --- 中学生、高校生のためのプライバシー問題へのヒント ---, 青空文庫, 1999年9月 |  |
 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題, 社団法人 全国求人情報誌協会, 1999年3月 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題, 社団法人 全国求人情報誌協会, 1999年3月
|
 |
 誰をどのように護るのか --- CDAの目的と効果について, 1999年1月30日, 情報処理学会 電子化知的財産社会基盤研究会にて報告. 情処研報, Vol.99, No.11. 誰をどのように護るのか --- CDAの目的と効果について, 1999年1月30日, 情報処理学会 電子化知的財産社会基盤研究会にて報告. 情処研報, Vol.99, No.11.
|
 |
 コンピュータ・ネットワークにおける自由と倫理, 1998年11月21日, 明治大学情報科学センター情報教育研究会にて報告. コンピュータ・ネットワークにおける自由と倫理, 1998年11月21日, 明治大学情報科学センター情報教育研究会にて報告. | |
 判例解説 Cubby, Inc. v. CompuServe Inc., 776 F.Supp. 135 (1991), 「アメリカ法」1998-1, 1998年7月31日 判例解説 Cubby, Inc. v. CompuServe Inc., 776 F.Supp. 135 (1991), 「アメリカ法」1998-1, 1998年7月31日
|
 |
 もう一つの著作権の話 --- 中学生、高校生のための著作権の基礎理論 ---, 青空文庫,1998年7月 もう一つの著作権の話 --- 中学生、高校生のための著作権の基礎理論 ---, 青空文庫,1998年7月
ボイジャーの野口さんのおかげで、こんなに立派な  になりました。 になりました。 |  |
 コピーライトの史的展開 [知的財産研究叢書2],信山社,1998年7月 コピーライトの史的展開 [知的財産研究叢書2],信山社,1998年7月
|
 |
 アメリカ著作権理論の起源 -- アメリカにおけるイギリス法継受の一事例 --, 報告用 手許資料, 英語版 (English version), 比較法研究 No. 60 (1999) 128. 1998年6月6日 比較法学会第61回総会 英米法部会. アメリカ著作権理論の起源 -- アメリカにおけるイギリス法継受の一事例 --, 報告用 手許資料, 英語版 (English version), 比較法研究 No. 60 (1999) 128. 1998年6月6日 比較法学会第61回総会 英米法部会.
|
 |
 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題 (中間報告書), 社団法人 全国求人情報誌協会, 1998年3月 求人・求職活動における個人情報保護に関する報告, in インターネット求人・求職情報の現状とその課題 (中間報告書), 社団法人 全国求人情報誌協会, 1998年3月
|
 |
 著作権の原理と現代著作権理論, 1998年1月31日 比較法史学会関東部会、2月2日 国際大学グローコム にて報告 著作権の原理と現代著作権理論, 1998年1月31日 比較法史学会関東部会、2月2日 国際大学グローコム にて報告
| |
 英米法系コピーライトに関する歴史的研究, 1997年5月 英米法系コピーライトに関する歴史的研究, 1997年5月
| 要旨 |
 情報テクノロジーの進展と法的課題 in 堀部政男・編著, 情報公開・プライバシーの比較法, 日本評論社, 1996年12月 情報テクノロジーの進展と法的課題 in 堀部政男・編著, 情報公開・プライバシーの比較法, 日本評論社, 1996年12月
| |
 アメリカにおけるインターネットへの司法権力の介入: IAJ News, Internet Association of Japan, Vol.3 No.1, 1996年4月 アメリカにおけるインターネットへの司法権力の介入: IAJ News, Internet Association of Japan, Vol.3 No.1, 1996年4月
|
 |
 比喩・概念・法 ---仮想空間を切り分けるもの(1)---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年11月 比喩・概念・法 ---仮想空間を切り分けるもの(1)---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年11月
| |
 アスペン・サミット オンライン ---ネットワーク時代の政府と共同体の役割---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年10月 アスペン・サミット オンライン ---ネットワーク時代の政府と共同体の役割---: Smart Community, Smart Community 研究会, 1995年10月
| |
 ハッカー倫理と情報公開・プライバシー:「高度情報化の法体系と社会制度」 科学研究費補助金・重点領域研究報告書, 1995年3月 ハッカー倫理と情報公開・プライバシー:「高度情報化の法体系と社会制度」 科学研究費補助金・重点領域研究報告書, 1995年3月
|
 |
 ネットワーク上の名誉毀損と管理者の責任: レポート, 1994年4月 ネットワーク上の名誉毀損と管理者の責任: レポート, 1994年4月
| |
 コピーライトの史的展開 コピーライトの史的展開
|
 |
 法令用語と判例における「情報」: 「情報の瑕疵がもたらす民事上の責任に関する調査研究」 財団法人 比較法研究センター, 1993年6月 法令用語と判例における「情報」: 「情報の瑕疵がもたらす民事上の責任に関する調査研究」 財団法人 比較法研究センター, 1993年6月
|

 個人的キャンペーン
個人的キャンペーン

個人的キャンペーンがあまりに多くなってしまった(^^;;ので別ページに移動しました。

 リンク
リンク

 ピカチュウずきの人におすすめ。 ピカチュウずきの人におすすめ。 さあ、いますぐピカ! さあ、いますぐピカ!

|


タイトルページを短くするために、「付録」を別ページに移動しました。参考資料や、私の雑文、秀丸のマクロなどがあります。

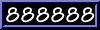
白田 秀彰 (Shirata Hideaki)
法政大学 社会学部 助教授
(Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences)
法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450)
e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp
法政大学 社会学部 助教授
(Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences)
法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450)
e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp