 コピーライトの史的展開(7)
コピーライトの史的展開(7)

──書籍業者の戦争(後編)および自然権論批判──
白田 秀彰
|
26 ドナルドソン 対 ベケット事件 ミラー事件の原告アンドリュー・ミラーの死亡の後、トムソンの『四季』 のコピーライトは、相続によって妻ジェーン、息子ウィリアム、トーマス・ ロングマンに移転された。そして、『四季』のコピーライトは、 故ミラーの遺言に従ってミラー事件での確定判決の後の1769年6月13日に「競り」 にかけられ、ドナルドソン事件の被告ベケット(Thomas Beckett)他14人に、 持分に分割されて 505ポンドで売却された [1]。 一方、ドナルドソン(Alexander Donaldson)はエディンバラの出版業者で、 1650年代から一貫して、1709年制定法の保護期間である28年間が満了した、 彼が信じるところの「世界共有」 となった版を出版してきた確信犯的海賊出版業者だった。 彼は海賊版出版業者として成功し、相当の財産を保有していた富裕者でもあった。 ドナルドソンは信念をもって、 ロンドンの書籍業者たちと闘争を続けてきた人物であり、 彼は自分の意見を法廷で明らかにすべく、 常にロンドンの書籍業者たちを挑発していた [2]。 こうして、ベケット他14人の『四季』の持分保有者たちが、 ドナルドソンの挑発に応じることになった。1771年1月21日に、ベケットは、 ドナルドソンによる『四季』出版の差止と金銭損害賠償を求めて大法官府に訴え出た。 1771年7月に、ドナルドソンは訴答を行った。その要旨は次の通り。
1709年制定法は限定された期間の排他的独占権を与えるものであり、 問題となっている『四季』はすでにその保護期間が満了している。 制定法の保護以外に『四季』に排他的権利を認める法的根拠はない。したがって、 自分が『四季』を出版し販売することは正当な行為である。 原告の主張する訴訟の目的は存在しない。しかし、ミラー事件で永久のコモン・ロー・コピーライトが確定している以上、 ドナルドソンの主張が認められる余地はなかった。1772年の11月16日には、 大法官アプスレー卿(Lord Apsley, Henry Bathurst)によって、 ベケットの全面勝訴の判決が出され、 本案的差止命令の発給と損害賠償が命じられたのである [3]。 ドナルドソンは、ミラー事件判決のことを承知していた。だからこそ、 ベケットを挑発して自分を告訴させたのである。 大法官府での敗訴は彼にとって好機だった。彼は1709年制定法6条に基づいて、 1773年にスコットランド民事上級裁判所に上訴した。スコットランドでは、 伝統的にコピーライトという考え方が存在せず、18世紀の終わりになっても、 コピーライトの存在を認めたと考えられるような判例は一つも存在していなかった。 そこで7月27日の審理において、スコットランド民事上級裁判所は、 12対1の大差でコモン・ ロー上の著作者の排他的財産権の存在を否定したのである [4]。 直ちに彼は、このスコットランドでの勝訴を基に、 貴族院に1772年の大法官府判決に対する誤審令状(writ of errors)の発給を請求した。 おそらく1773年末には上訴が認められたものと思われる。こうして、 ミラー事件と双璧をなすコピーライト史上の重要事件、 1774年のドナルドソン他 対 ベケット他(Donaldsons v. Becket and Others, / Alexander Donaldson, and another v. Thomas Beckett, and Others)事件 [5] が始まるのである。 この事件の詳細を知るためには、 English Reportsに収められている裁判記録だけでは不十分で、 Parliamentary History of England [6](以下、 「Parliamentary History」)を参照する必要がある。 これによると審理が開始されたのは2月4日で、間に日をおきながら審議が続けられ、 2月22日に結審している。その間、原告・被告双方の弁論、 財務府会議室裁判所への諮問、貴族院議員による裁決が行われている。 この事件に言及する研究で、 しばしば財務府会議室裁判所での多数意見がこの事件を決したように扱われている。 しかし、貴族院での審理ではあくまでも貴族院議員が審判するのであり、 財務府会議室裁判所に参集した裁判官の意見は補佐的なものにとどまることを指摘し ておく [7]。
26.1 ドナルドソン側の主張審理ではまず原告側、すなわちコモン・ ロー上のコピーライトの存在を否定する側が弁論に立った。 この時の論者は1760年トンソン事件、 1769年ミラー事件において被告側の弁護にあたったサーロー氏で、 彼はいまや法務総裁の要職にあった。彼の論述した内容は、 以前の事件での彼の弁論の内容とほぼ同一なので割愛する。しかし、 彼の問題意識と態度を示すために結語部分を示す。
「スコットランド民事上級裁判所は、 文字的財産の存在という奇妙な考え方から生じる独占からスコットランドを自由にし た。同様にこの裁判でも、同様の決定をすることで、他者の労働、発明の成果、 才能の結果から不当な利益を得ている少数の独占的書籍業者の手から、 文芸と著作者を救い出すことが現在の核心的問題なのである [8]」彼は以前から、コピーライトの問題を独占との関連で捉えていたのであるが、 彼のこの弁論はドナルドソン事件の審理の方向を予告するものとなったのである。 つづいて2月7日、ダリンプル(John Dalrymple)弁護士が原告側から弁論した。 彼はまず歴史を引きながら、コモン・ロー・コピーライトの存在を否定する。そして 「コピーライトは利益の高い出版物をめぐる書籍業カンパニーの構成員の間の争いに 起源を持ち、それぞれがある作品を出版する権利を “財産” と呼んだことが一般にそのような印象を与えるようになったに過ぎない [9]」と指摘する。 つづいて、1709年制定法の文言を引きながら、 1709年制定法は著作者に新しい権利を与えたものであると結論する。そこで、 1709年制定法の性格について興味深い見解を示す。彼が主張するには、 著作者にコモン・ロー上の権利が存在しなかったからこそ、 出版勅許が存在していたのである。しかし、勅許によるならば、 著作者は勅許を与えてくれる保護者に従属することになり、 保護者の意に沿わない学問が抑圧されることになる。 そこで著作者を保護者の影響力から解放するために、制定法をもって「一般的特許」 (universal patent)を与えたものである、というのである。 また、コモン・ロー・コピーライトに反対する原告側が勝訴することが、 著作者たちと産業の双方にとって収益の増加をもたらすという点で有益であると主張 する。というのは「書籍業者たちの手元にある古い版が共有となれば、 書籍業者たちは、著作者たちに新しい作品の供給を求めるだろう。そこで、 書籍取引だけでなく著作者たちも利益を受け、 著作者たちの獲得する収益も十分に増加する [10]」からである。 さらに彼は次のようにもいう。「12人か13人の書籍業者たちが、 死骸の上にたかる禿鷹のように、 不幸なトムソンの遺産の上を飛びまわっている [11]。」 26.2 ベケット側の主張続く2月8日、被告側の弁論が行われた。最初に弁論を行ったのは法務次長 (Solicitor General)ウェダーバーンである。 彼は1760年トンソン事件の原告側弁護士だった。彼の行った弁論は、 トンソン事件の時とほぼ同一内容なので割愛する。つづいて、被告側弁護士ダニングが弁論した。 彼はウェダーバーン法務次長の弁論に付け加えて、原告側が主張する 「公表によって作品は共有となる」という主張を批判する。「著作者がコモン・ ロー上の権利を保有しているとして、仮に彼がその財産権を行使しようとした瞬間に、 それを失うというのは奇妙な論理に思われる [12]」。したがって、 著作者の権利は、作品の公表の後にも存続するというのである。 また、彼は、ダリンプル弁護士の主張に反駁する形で次のように述べる。すなわち、 出版と同時に誰もが複製できるのならば、出版者は収益が上げられないから、 著作者に利益を与えることができなくなる。ミラー事件でコモン・ロー・ コピーライトが認められて以来、 著作者は十分な利益を受けることができるようになった。 原告の訴はこの利益を侵害しようとするものであり、 それは著作者の利益の侵害なのである [13]、と。 原告・被告双方の主張を概観していえることは、以前の事件で述べられた主張に、 新たに「独占」と「利益」の視点が付け加えられているということだろう。 原告側はコモン・ロー・コピーライトの概念は永久の独占を導くものであり、 その独占は著作者と書籍産業双方に害悪となるとする。一方、 被告側は出版者の収益が著作者の生活を支えているのだから、 出版者の利益は保護されなければならないとする。 被告側の論理について検討すれば、詭弁を見つけることができる。 被告側が主張する利益の保護は、1709年制定法で期間を限って与えられているので、 零ではないはずである。しかし、彼らはそれ以上の保護を求めている。一方、 どの程度の期間の保護が、 出版者が著作者に十分な報酬を与えることができる利益を保障するのかについては主 張しない。ここで、 彼らは自然法から導かれる作品についての著作者の永久の精神的所有権をもち出す。 そして、出版者の利益保護の必要性と、 自然法上の著作者の永久の精神的所有権を結合することで、 永久の保護期間を主張しようとしているのである。原稿買取制度の下では、 出版者が著作者に与える対価は有限である。一方、 永久の保護期間の下では出版者は無限の利益を想定することができる。
26.3 諮問翌2月9日、法務総裁サーロー氏が訴答を行っている。ここで、 彼は昨日の被告側の弁論について反駁するのだが、コモン・ ロー上の著作者の権利に関する哲学的論拠、大法官府の差止命令が示す意味の解釈、 1709年制定法の文言の解釈で被告側との水掛け論に陥りつつあった。おそらくこのため、コモン・ ロー裁判所を構成する12人の全裁判官から構成される財務府会議室裁判所へ諮問する ことが決定されたのだと思われる。そして、次のような論点が設定され、 それぞれの裁判官が貴族院に意見を提出することが求められた [14]。
この諮問の結果は、2月15日から21日の間に順次~貴族院にもたらされるのであるが、 いちいちを検討するのは紙幅をとりすぎるので、一覧にまとめる。 ここで一覧にする関係上、 それぞれの裁判官の主張のこまかな差異が均質化してしまうことになることは容赦ね がいたい [16]。また、表中“Baron” と表記されている人物は財務府会議室裁判官である。
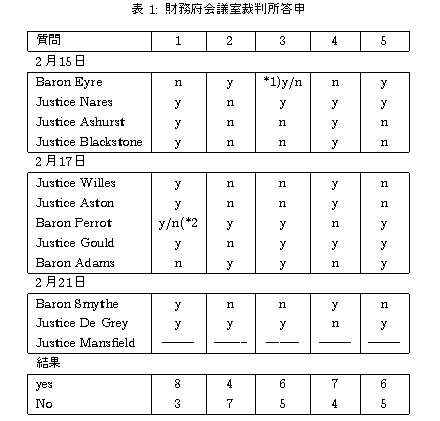
イヤー(Eyre)裁判官の意見中、[*1]について彼は、もとよりコモン・ ロー上の権利の存在を否定していることを前提として、 仮にそのような権利が存在するとしても、制定法の保護期間を越えてコモン・ ロー上の保護は存在しないとする。しかしながら、不法な原因で侵害が生じた場合、 衡平法上の保護が与えられることは否定しない。その理由として、 この事件に先行する大法官府における差止命令の発給を挙げ、 それらは被告側の不法な行為に由来するとしている [17]。 アシュースト(Ashurst)裁判官、ブラックストン裁判官、ウィレス裁判官、 アストン裁判官は、いずれもコモン・ローに基づくコピーライトによって、 制定法の保護期間の後にもコモン・ロー上の救済が与えられるとする。 ブラックストン裁判官は、1761年トンソン事件、 1769年ミラー事件で原告側の弁護を担当している。ウィレス裁判官、 アストン裁判官は、いずれもミラー事件で原告側の弁護を担当している。 彼らの意見は、それぞれの担当した事件で述べられた内容とほぼ同一なので割愛する。 またブラックストン裁判官は、このとき痛風を理由に欠席し、 意見書をアシュースト裁判官に託していた。 ペロー(Perrot)裁判官の意見中、[*2]について彼は、著作者が原稿についてコモン・ ロー上の権利をもつことは明らかであるとするが、ただし、コモン・ロー上の権利は、 その物質的部分についてのみ認められるとする。すなわち、 観念的な支配権については否定し、原稿を保有している限りでそれはコモン・ ロー上の財産であるとするのである [18]。 「他者が版を複製し利益を獲得することで、本来の著作者の損益(loss)とはなるが、 しかし、その他者が権利侵害(injury)を働いたわけではない。 権利侵害では権利が損なわれることが必要である。その権利はコモン・ ローに基づかなくてはならない [19]」という言葉からわかるように、 彼は観念的な「内容」について財産権が認められないと主張しているのである。また、 彼は先行する大法官府の差止命令について、「仮に彼らがそれら[差止命令] を制定法の内容に基づかずに発給したのであれば、 大法官府は全体として法を誤ったのである [20]」と述べている。 財務府会議室裁判所首席裁判官スミス(Smyth)は、 とくに人格権的発想でコピーライトに言及している点で注目される。 「著作者の本を複製することは、著作者の考え方を盗むだけでなく、 彼の名誉も奪うことになり、 その海賊版は本来の著作者の作品として世に出されることになる。このため [出版後に著作者の権利がなくなるとするならば]著作者は、 彼の正式な第1版でも避けられなかったいくつかの誤りを訂正することができなくな るし、また最初の出版の後に[海賊業者によって] 付け加えられた誤りを削除することもできなくなる。 このことは不当である [21]。」 最後に、マンスフィールド卿は意見を述べなかった。 彼はミラー事件の判決理由の中で自ら語っているように、 数多くのコピーライト訴訟に関係し [22]、 コピーライトについて最も詳しい人物だったはずである。また、 著作者の権利を世界で最初に確認した裁判の首席裁判官として、 確信をもってドナルドソン事件での被告を擁護することができたはずである。しかし、 彼は何も語らなかった。これについてBurrow's Reportでは、“It was notorious” と評されている[23]。というのは、 おそらく被告側有利、すなわちコモン・ ロー上の著作者の財産権を支持する彼の一票があれば、(3)、(5) の問いの票数の諾否が均衡し、 あるいはこの事件の結果に影響を及ぼしたかもしれないからである。なぜ、 マンスフィールド卿は意見を述べなかったのだろうか。 さて、以上のように財務府会議室裁判所の意見がそろえられた。 そして貴族院議員による裁決が行われることになった。ここで、(4)、(5) の問いを設定したカムデン卿が演説を行っている。 その内容は非常に強い口調でこれまでの裁判官たちの意見を弾劾し、著作者のコモン・ ロー上の権利をうそぶく独占的出版業者たちの独占を批判する内容になっている。 「被告側から述べたてられている議論は、勅許、特権、星室庁布令、 書籍業カンパニーの規約に基づいている。それらの全ては暴虐な専制と [人民の権利の]剥奪の結果であり、それらのどんな些細な部分でも、 この王国のコモン・ ローの形跡を見つけることができるなどとは夢にも思えない [24]。」そして、 被告側の意見が無理に事実をねじ曲げて、コモン・ ロー上の権利を作りだそうと努めていると批判し、被告側論者が雑多な哲学上、 歴史上の資料などを並べたてることについて「それは、議員諸君を混乱させ、 議論をあらぬ方向に逸らすために仕組まれただけなのである [25]。」「この法廷で、 いま求められているコモン・ロー上の権利は、国王にも、カンパニーにも、 全ての人類にも顧慮することなしに、 ある作品を永久に印刷する権利を私人に与えるものであることを常に思い起こしてい ただきたい [26]」と、 この事件の実質が独占の問題であることを強調する。 彼は弁論の終わりのほうで次のように述べている。「我々の学問の全てが、 その時代のトンソンやリントン(Linton) といった独占者たちの手に縛り上げられ、 その独占者たちは、 彼らのいいかげんな雇われ編集者たちと同じように社会全体が彼らの奴隷と化すまで、 自らの貪欲さが欲するままに価格を付けることになる [27]。」 これまで筆者は本論文で、訴訟記録だけではなく、 その背景となっている社会事情についてもできる限りふれてきた。 それゆえコピーライト訴訟の背景となってきた独占について、 なぜ法廷で採りあげられないのかと不思議に感じていた。 その理由について次のようにまとめることができるだろう。 法廷の密室では部外者の目から逃れることができたが、イギリスの最高権力機関、 貴族院では「常識」(common sense)の目から逃れることはできなかったのである。 カムデン卿は、 書籍業カンパニーの規約と星室庁布令によってコピーライトが存在していたという議 論について、鋭い批判を浴びせる。「それら [カンパニーの規約と星室庁布令によるコピーライト]が確立されていたとしても、 そのカンパニーに依存することなしに著作者はどのようにして印刷すること、 すなわち彼に与えられていたという権利を行使する余地があったのだろうか? [28]」また、 1681年の書籍業カンパニーの規定を引き合いに出しながら、「それらは彼ら [書籍業カンパニー] がなんとかして全ての版を彼ら自身の手に収めようとするため [29]」の策略だったとする。 彼の批判は、弁護士や裁判官たちにも容赦なくそそがれる。 「弁護士たちの議論など全くの空論であり、ほとんどの事件で、 そこで述べられている議論は依拠するには実に危険なものである。しかし、それらの “でたらめ” についてここで論及することを私は恥と感じる [30]。」また、 差止命令の存在がコモン・ ロー上の権利を暗示するという主張について次のように皮肉をいう。 「いつから大法官はコモン・ロー上の権利について決定する権限を獲得したのか? [31]」 さらに批判は被告側が主張する「文字的財産」自体に及ぶ。 彼は “Literary Property”という言葉以外に、述べたてられる権利がコモン・ ロー上のものであるという雰囲気を漂わせるものは見あたらない、 とした上で被告側論者を次のように罵倒する。「彼らはコモン・ ローから一つの言葉を借りてきて、なんとか、 彼らがいうところのコピーライトの実体にあてはめるため、 がらくたのような資料をそれぞれの納屋(コピーライトをコモン・ ロー上の権利だと主張する論者の頭)にかき集め、 その権利が示すだろうようないくつかの原理を導きだし、そして、 それによって物事を判断したのである [32]。」そして 「これらのような曖昧な権威から引き出された議論に我々がこれほど長く幻惑されて いたことは驚きである [33]」 と嘆ずるのである。 以上のカムデン卿の辛辣な批判は、筆者が都合よく編集しなおしたものではない。 カムデン卿はこれ以上の辛辣さと綿密さをもって、批判を展開しているのである。 また、彼の見解が貴族院で奇異なものと受け取られなかったことは、 彼の弁論の後に行われた採決で、 23対11という大差をもってミラー事件判決の逆転が確定したことに示されている [34]。
27 ベケット事件後 貴族院のベケット事件判決での「コモン・ロー・コピーライトによる永久の保護」 の否定のため、 ミラー事件で一度は確定したコピーライトの永久保護は約5年間で終了した。 この判決は、ロンドンの書籍業界に大きな衝撃を与えた。 ベケット事件判決の5日後には、「自分たち自身、 およびコピーライト保有者のためのロンドンとウェストミンスターの書籍販売業者た ちによる請願」[35](以下、 「1774年請願」)が庶民院に提出され、 ベケット事件で確定した司法上の決定を議会の制定法によって再度覆そうとする試み が見られた。一方、これに対抗して、ドナルドソンの一派から、 反対請願が提出された。そこで庶民院では、 双方の関係者を議会に召喚して意見を聞いた [36]。 請願の審議は委員会に付託され、3月24日にその委員会から報告書が提出された。 そこでは、1774年請願に参加した87人の人物は、コモン・ ロー上のコピーライトが1709年制定法によって剥奪されるとは考えていないと主張さ れており、また、 1755年以降すでに49,981ポンド5シリングがコピーライト購入のために費されている ことが述べられている。すなわち、 既成事実化している永久のコピーライトの存在を認めて欲しいというのである。また、 この報告にはジョンストン(William Johnston) のコピーライトに関する詳細な調査報告が附属されており、 その内容はロンドン書籍業界の意にそった内容に仕上がっていた [37]。 報告書の内容に対する批判があったものの、 請願者たちに議会へ提出する草案を作成するように指示が出され、「限られた期間、 著作者あるいは彼らの指定した人物からからそれらの版を購入したものに印刷された 書籍の版を帰属させることで、書籍販売業者を助ける法案」 [38](以下、「1774年法案」) という法案が作成された。草案の原文は残っていないものの、その内容は、 1709年制定法で保護が及ばなかった版についても保護を与えるものである上に、 既存の保護期間をさらに延長するものだったという [39]。 この法案は4月22日に庶民院で第一読会に付され、5月10日には、第二読会に付された。 議会で審議が進行していることに不安を抱いた反独占勢力からは、 少なくとも5通以上の反対請願が提出された。これらの反対請願は(1) エディンバラの書籍業界、(2)ロンドンとウェストミンスターの小売業者、(3) グラスゴーの書籍業界および大学、(4)ドナルドソン、(5) ヨークの書籍業界からのものである [40]。このことから、 1774年請願はコンガーたちだけから申したてられたものであること、逆に、 イギリスの書籍業界一般はロンドンのコンガーたちの市場独占に反対していたことが うかがわれるのである。 5月10日にはベケット事件でドナルドソンを弁護したダリンプルが、 議会で発言することが許された。ここで彼は、 コンガーたちが新聞に金を支払い自分たちに有利な記事をかかせ、 世論を永久のコピーライト支持に誘導しようとしたり、 あるいはグラスゴーの書籍業界に有利な取引条件を示すことで懐柔をはかったりとい った工作を続けていることを報告している。 新聞を使った世論誘導は実際に行われていた証拠がある [41]。 一方、5月13日には、 ミラー事件の首席裁判官マンスフィールド卿が議会での発言を許され、 ロンドンのコンガーたちの弁護を行った。まず彼は、 1759年の反輸入書籍運動機構が集めた資金が、訴追のためではなく、 知らずに違法書籍を購入した地方書籍販売業者から違法書籍を買い上げるために利用 されたことを述べた。すなわち、 コンガーたちが穏やかな手法で対処しようとしたこと、 またその資金が議会や法廷への工作資金として使用されなかったことを主張している のである。また、ドナルドソンの出版物の内容が不正確であること批判し、さらに、 1774年ベケット事件判決の影響で、地方に技術未熟な印刷所が次々と設立され、 イギリスの文芸が危機に瀕していること、 出版業という商売が通常の商売とは性質が異なる特殊なものであることを挙げ、 出版業に何らかの規制が必要であることを主張した [42]。 彼が述べたイギリス文芸の危機というのは全くの逆だった。 永久のコピーライトが廃止されることで、 18世紀末から19世紀初頭にかけて復刻版が流行し、 新規の書籍業者たちが市場に多数参入した。彼らは、書籍の価格を引き下げ、 新しい需要を喚起することで、結果的にはイギリス文学の底辺を広げた。 そして19世紀以降、 出版業者たちはより多くの収益を得ることができるようになったし、また、 古典だけでなく新作の需要が高まることで、 文筆家たちも大いに潤ったからである [43]。マンスフィールド卿の主張は、 コンガー側の主張に偏ったものだった。このことから、ミラー事件判決を導き、 ベケット事件で沈黙した彼が、 ロンドンの大手書籍販売業者たちと親しかったことがうかがわれるのである。 5月26日に、1774年法案は、貴族院での第三読会に持ちこまれた。 貴族院ではベケット事件の審理が再現された。デンバー卿(Lord Denbigh)、 大法官アプスレー卿、カムデン卿の三者が反独占の立場から法案を激しく批判し、 廃案に追いこんでしまったからである。こうして、 ベケット事件で示されたコピーライトの理論は揺るぎなく確定したのである [44]。 彼らの主張が正しかったことは、 先に述べたイギリス出版界の 19世紀における繁栄が証明している。 ベケット事件の翌年、 1774年の書籍業カンパニー 対 カーナン (Stationers' Company v. Carnan)事件 [45]の人民間訴訟裁判所判決に続く、 1775年6月の貴族院判決で、 英語版株で最も収益の高かった暦の出版勅許も無効となった。こうして、 1770年代のなかばをもって、 イギリスのコピーライト制度は国王大権の影響力を完全に払拭し、“法律的” には議会の制定法に基づいた運用に委ねられることになった。
28 1774年以降の概観
28.1 法律と実態の分離ベケット事件判決にも拘わらず、1774年の後にも「株」としてのコピーライト運用と 「競り」による取引の機構は機能し続けた。チャプター(Chapter) 珈琲店に集まる婚姻・血族関係を中心に結び付いた大手出版社の経営者たちによって、 書籍業者たちの“事実上” のコピーライト機構は長く維持されることになったのである [46]。1774年以前に、 永久のコピーライトを前提としてコピーライト持分に付けられていた価格は、 ベケット判決のため暴落するのが道理である。しかしながら、 1774年以降も以前と変わらずコピーライトの価格は上昇を続けたのである [47]。また、1813年に、 年間834ポンドの収益を挙げていたカウパー(Cowper)の詩集のコピーライトが、 保護期間が残り2年となった時点で「競り」で売り出されたところ、 6,764ポンドで落札されている [48]。 購入者が、制定法による保護期間の満了後にも、 コピーライトが出版業界内部で実質的に尊重されることを期待していることが落札価 格に現れている。
28.2 国外への影響コピーライトという権利がイギリス国外へ与えた影響を考えるとき、 『イギリス法釈義』が当時の法律書としては異例のベストセラーだったこと、 とくにアメリカで重用されたことを考えれば [49]、『イギリス法釈義』 の記述内容が重要な要素となる。そこで、 先に検討したのはベケット事件の前に出版された第4版だったので、 ここではベケット事件判決の影響を見るために、 ブラックストンの生前の最終版である第10版 [50] を第4版と比較しながら検討する。まず、冒頭において、著作者が執筆活動によって獲得する権利について、 「仮にそれがコモン・ ローによって支持されるとして (if it subsists by the common law)」 という限定を括弧書きで挿入している。 次いで、第4版で“....any attempt to take it from him, or vary the disposition he has made of it, is an invation of his right of property ” とされている部分から第10版ではイタリック部が取り除かれている。 この変更を後の部分と照らしてみると、これはブラックストンがコモン・ロー・ コピーライトを譲渡不能の権利として把握した事を示し、さらに、 その権利が財産権のみではないと把握した事を示している。 これに続く部分では、第4版で“convey”として表現していた部分を第10版で “exhibit”という単語に置き代えている。これは語感の問題であり、 あまり重要な変更ではないだろう。 次に、 「他の誰もそれを提示する権利を持ちえない (no other man † can have a right to exhibit it)」という部分に「と考えられている(it hath been thought)」 という括弧書きを挿入して(† の部分)、表現をやや弱めている。また、“it” に続いて、「とくに経済的利益について(especially for profit)」と挿入して、 他者が著作者の権利を行使するとき、 とくに経済的利益が問題となる事を強調している。 これに続いて、作品が公的領域に入る条件について述べた部分において、 「本に所有権の票章を刻印せずに (without stamping on it any marks of ownership)」と並んで、第10版で 「権利の留保なしに(with out any claim or reserve of right)」 という語句を挿入し、必ずしも票章を本に印す事を要求せず、 他の方法による権利主張によっても作品の権利が保護されることを示している。 これに続く26章8節1段落末尾が大幅に加筆されている。ここでは、本(原稿)の売却 (sells a single book)あるいはコピーライトの譲渡(totally grants the copyright) がなされても、購入者が持つことのできる権利は販売のための複製にとどまるとする。 しかしながら、すべての財産権はすべての排他的権利とともに、 永久に購入者に移転するとする(the whole property, with all it's exclusive rights, is perpetually transferred to the grantee.)。 自然権上の「著作者の権利」と営利的利用権である「コピーライト」 を分離している事がわかる。 一方、 印刷や公表がなされる前にはすべての権利が疑いなく著作者に帰属するとするが、 公表した瞬間に、その著作を伝達する排他的権利 (right ....to the sole communication of his ideas) は消滅 (vanishes and evaporate)するとする。したがって、その権利はコモン・ ロー上の財産権としては非常に弱いものとなるので、実定法 (positive statutes and special provisions of magistrate) によってのみ保護されるのであるとする。 ブラックストンは公表後の排他的権利について、 それが実定法上のものであることを明言しているのである。 続く第2段落の、 ローマ法についての言及においても表現が変わっている部分があるが、 こちらは些細なものにとどまる。ただ、第4版で、大法官府の差止命令発給で、 コモン・ロー上の権利がイギリスにおいて認められてきた、としていた部分を削除し、 「イギリスにおいてもコモン・ロー上の『著作者の権利』 については近年にいたるまで何らの最終的な決定はなされていなかった」 と変更している。ベケット事件判決が影響している事は明らかである。 最後の第3段落では、制定法上のコピーライトについてふれている。ここでは、 1787年までに制定された制定法を紹介しながら、本来のコピーライトは、コモン・ ロー上で支持されるのであるが、1709年制定法によって、 限定された期間の権利と権利侵害への罰則が与えられているとする。 全体的な改訂は、1774年ベケット事件判決を正確に反映したものであり、 トンソン事件当時にコモン・ ロー上の財産権を強硬に主張したブラックストンの立場を考慮すれば、 実に潔く変更されていて、学者としての彼の公正さを印象づけるものとなっている。 しかし、 自然権にコピーライトの基礎を求めるという基本的な枠組みが変更されていないため、 おそらく、後の世代の学者が「著作者の権利」と「コピーライト」 を混同したのだろうと思われる。このため、“自然権を基礎とするコピーライト” という考え方は、 ベケット事件貴族院判決を知るイギリスの法曹などの限られた人々を除いては、 依然として流布したのである。
29 コピーライト理論 1774年ベケット事件判決で確立したイギリス法系著作権保護の仕組みは、 次のような構成をとることになった。 まず、著作者が創作物について実質的占有を維持している場合には、 その創作物についてコモン・ロー上の財産権、 すなわち一般的な所有権と同様の権利を持つこととされた。 著作者が媒体に内容を固定した瞬間に、媒体のみならず内容にも財産権が生じ、 その内容を一定の要件のもとに公表しない限り、 内容についての実質的占有があるとみなされ、 この未公表の作品についての財産権の侵害はコモン・ ロー上の財産権侵害として訴えることができる。このコモン・ ロー上の保護は期限がなく、永久のものとされる。 一方、著作者が創作物を売却あるいは譲渡その他の方法で公表してしまい、 実質的占有状態がなくなると、その創作物は公的領域に入ってしまい、もはやコモン・ ロー上の請求をすることはできなくなる。しかし、 著作者の利益保護が必要であるため、制定法で、 限定された期間の排他的独占権を与える特許を著作者、 あるいはコピーライトを譲り受けた人物に与えることで保護することになる。 制定法上のコピーライトは登記と同時に無審査で生じる。 逆に登記を懈怠すると制定法による保護は制限される。また、 コピーライトに関しては、コモン・ロー上の保護および制定法上の保護のいずれも、 財産権的側面(property)の保護にとどまり、人格権的側面(moral right)については、 他の一般的人格権保護の法理によって処理されることになる。 この仕組みはイギリスで1911年まで、アメリカでは 1988年まで維持された。
30 小括 15世紀初頭から18世紀の終わりまでの約400年間を、 コピーライトを追いながら概観してきた一連の連載も、 ここで一つの区切りをおくことにする。次のコピーライトに関する研究は、 英国植民地時代の北部13州から説き起こし、 現代アメリカの制度に至るものにしたいと考えている。というのは、 筆者の根本の目的はアメリカのコピーライト制度を理解し、 これから生じるであろう日米の知的財産を巡る議論の基礎を固めることにあるからで ある。すなわち、ここまでの研究はその最も根本を探るものだったのである。 図1は、縦に時間軸を取り、これまでの一つ一つの章が、 全体のどこに位置づけられるかを示したものである。
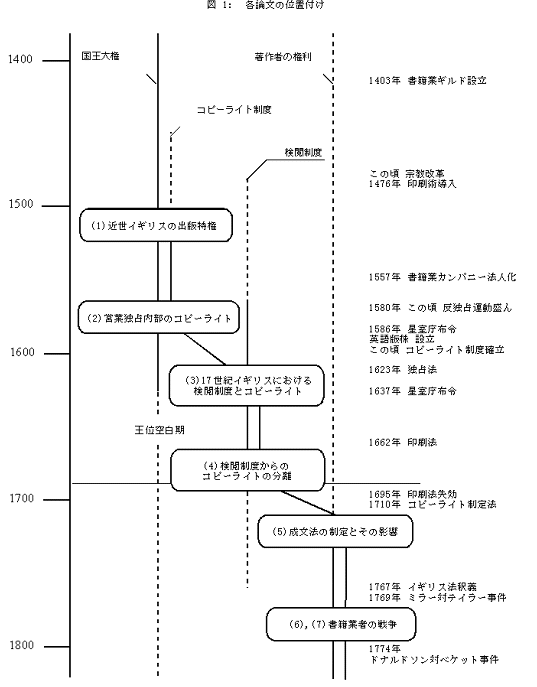
さて、事業者の営業利益を保護する「排他的独占権」、すなわちコピーライトは、 当然に保護されるべきである。現在では、 創作者のみならず多数の当事者がコピーライトに依拠して経済活動を行っているし、 コピーライトによって知的創造を経済的価値に変換することで、 創作者たちは生活の基盤をえることができ、その結果、 創作活動は奨励されてきたのである。 それでは、「創作者(著作者)の権利」はどうであろうか。 創作者が自己の作品から経済的利益を獲得すること、自己の名声を守ること、 自己の作品の同一性を守ること、 いずれも著作権によって保護されることになっている。しかし、 一部の人気作家を除いて、 売文によって生計を立てる人々や企業で従業員として創作活動を行う人々、 あるいは印刷術の登場当時から経済的に成り立たなかった学術出版に依存しなければ ならない学者たちの地位は 18世紀以来 大きく向上しただろうか。「創作者の権利」 を保護しているというベルヌ条約法系の著作権は、 創作者本人を保護しているのだろうか。 本論文では18世紀以降の著作権の歩みを見ていないので、ここでは、 結論を出すまでには至っていない。 しかし、筆者が考えるに、「排他的独占権」を与えて「創作者の権利を保護している」 というのが詭弁にすぎないのは、18世紀末も現代も同様であると思う。というのは、 排他的独占権は経済的に成功した作家、 あるいはこれを利用して営業する企業家のみに意味のある権利であり、 大多数の創作者は、 むしろ自分の作品をいかに世に送り出すかに難儀しているからである。 それどころか近年は、排他的独占権の存在が新しい表現形態・ 伝達形態の発展を阻害する事例もあるように思われる。学問・芸術・ 文化の発展という著作権法の目的に立ち返り「排他的独占権」の害悪を除去する事は、 決して「創作者の権利」を縮減することにはならないのではないか。
31 自然権論批判 歴史的検討では、排他的独占権は産業上のものであり、 創作者の権利とは後に結合されたことが明らかになった。 その結合の過程で最も強く主張されたのは、ロックの財産権論であり、 なかでも加工の論拠だった。すなわち、 「自らの手によって生み出されたものはその人に属する」と。著作権は、 現在も一般に「創作者の権利」と理解されており、 その権利の源泉は加工あるいは占有に由来する自然権にあるという。 そこで本節では、 ロックの財産権論から現在の著作権制度で保障されている排他的独占権が導かれうる のかを検討する。そこで明らかになるのは、 創作物の公表以前の実質的占有状態を維持することが永久の排他的独占権の前提であ り、創作物を公表して経済的に利用しようとした瞬間から、 それは実定法の示すところに従うというものである。このことから、 排他的独占権を実定法上の権利だとする説、 またはそれが自然法上の権利だとする説のいずれをとっても、 ロックの自然権理論を援用する限りでは、 排他的独占権の内容および存続期間は実定法に従うことが明らかになるのである。
32 自然権論と著作権理論 さて、これまでの論述で、著作物が著作者に所有される、 という考え方が登場するまで検討してきた。 この後の学説の形成についての詳細な検討は半田正夫『著作権法の研究』 [51]の第一章でなされている。 そこでは、各学説が、精神的所有権論、人格一元論、二元論、droit double論、 新精神的所有権論、著作権一元論に分類され整理されて紹介されている。 精神的所有権論が書籍業者たちの出版所有権論を裏付けるために登場したという過程 は、本論文におけるこれまでの論述でも明らかになっている。 欧州でもこの展開は同様だった。したがって、 ドイツの学説でも精神的所有権論の根拠は自然法に求められており、 「共通の主張は無体物たる著作物についての排他的権利を著作者固有の権利として承 認し [52]」ている。 また、人格権一元論は、 刑法の面から偽版を取り締まるために構成され [53]、 保護の客体を人格であるとする。ここでも、「著作物は人間精神の発露であるから、 著作者は創作者と創作物との間の関係に見られるごとき自然権を有する [54]」と主張されており、 自然権を理論の根拠に据えている。そして、人格権からの演繹の結果は、 経済的利用の局面でも著作者の排他的支配が全面的に及ぶことを主張するのである。 これに続く、二元論、droit double論、著作権一元論は、基本的には、 精神的所有権論と人格一元論を現実の著作権処理の中で調和させることに努力してお り、それぞれの理論の違いは、 人格権と財産権の交錯領域をどのように理論づけるかの違いであると理解される。 すなわち、 自然権に由来する著作者の著作物への排他的支配が所与の前提とされている点でいず れも同一の基盤に立っているのである。 これらの諸理論について批判するならば、著作権法で通常の手法となっている 「限定された期間の排他的独占権付与」をどのように説明するかという疑問である。 まず、創作者への創作物の帰属を強調すれば(人格一元論が該当する) 彼の死とともに保護すべき財産権・人格権は消滅するはずである。一方、 創作物が創作者の生命とは独立の財産であるとするならば(精神的所有権論、 細かな構成では違いが見られるが二元論、droit double論、 著作権一元論が該当する)、著作物が存続する限り、 正当な相続者が独占権を行使し続けることになるはずである。 精神的所有権論を除くそれぞれの論では、 創作者の人格が彼の死後一定期間存続することを理由に、 あるいは死後一世代が経過すると創作者の人格的利益が衰微することを理由に、 著作者の死後一世代程度の著作権の存続を認めている。しかし、 その権利の時間的消滅については、それぞれの理論から導かれたのではなく、 自然的感情あるいは経験的合理判断から根拠なく導かれているとしか考えられない。 また、現代社会でも個人の創作者が創作の原動力となっていることは明らかであるが、 それ以上に企業が多数の労働者を指揮して創作活動にあたらせる場面が増大している こと、また、 大きな商品価値を持つ著作物が企業の投資を前提としなければ成り立たなくなってい ることを認めなければならない。著作隣接権を導入し、 あるいは法人著作の規定を持つ以上、法人(企業) が排他的独占権を行使する場面が生じるが、それらが享受する保護期間について、 精神的所有権論を除くこれらの理論はどのような説明をするのだろうか。 仮に法人に人格性を認めるならば、 それは純然たる独占を擁護する理論になりはしないだろうか。
33 自然権論と排他的独占権 現在の著作権法のモデルを形成したのが1709年制定法であり、 その1709年制定法の内容を自然権と結合したのがブラックストンであるならば、彼が 『イギリス法釈義』[55] で述べているとおり、ロックの自然権論がその基礎となっているはずである。また、 多数の著作権理論が援用する「他の誰のものでもない自分の頭脳の労働の所産として、 自らの創作物を占有するのである」という考え方はロックの『市民政府論』 [56]の「財産」 の部分に起源があるのである [57]。 したがって、精神的所有権論者のいう自然権とはロックの自然権ということになる。 そこでロックの自然権を検討し、 排他的独占権にはいかなる限界があるのかという点について考察する。
33.1 自然状態ロックの描く自然状態の前提は「神が『地を人の子に与え給い』、 すなわちそれを人類の共有のものとして与えた [58]」ことにある。そこで、 神が人類に理性を授けたというロックの解釈 [59]に立てば、「地」も「理性」 も神の与えた物として同一であり、 この前提は人類の知的領域について拡張して解釈しうる。 ロックによって想定された自然状態は次のような条件のもとにある [60]。(1)財物は潤沢にある。これらを知的領域に類推するならば、それぞれ対応する部分を (1a)創作における選択の多様性が十分に大きい。と読み換えることが可能である。(1a)(2a) の条件は芸術の分野で現在でも適合する条件であるし、 芸術の分野では剽窃でない限り(7a)の条件も適合するだろう。 自然状態から他への移行は(4)の条件と(5)の条件が否定されることに始まる。 すなわち国家を形成するという協定と [61]、 貨幣を利用して一つの価値を表象するという黙示の協定である [62]。ロックの議論では、 貨幣によって現実の財産状態の格差が説明され、 その格差は貨幣を使用することで暗黙に承認されているものとする [63]。
33.2 所有の論拠ロックの議論では、何かが人類の共有領域から私有されることについて、 人類の共同利益とそれらの獲得された利益が競合することがないという前提に立って いる。 それは同じだけの共有領域が十分に残されているという仮定によっている [64]。生存権から導かれる論拠について検討する。 知的な創作については実際の諸物と違って、 万人共有に属するものを自分の占有に帰する自然的権利がなければ 「餓死する [65]」 ということはない。創作は多数の人で同時に享受可能だからである。しかし、 それが生命・自由・所有の権利、あるいは生命・健康・自由・ 私有財産の権利 [66]と関係する時、 すなわち職業的創作者が存在するならば、 それを占有に帰する自然的権利があると演繹できる。というのは職業的創作者が、 自己の創作物を誰かと交換することで生活しているのなら、 他者がそれをまねて彼の顧客を奪う事は彼の生存を脅かすことになるからである。 このようにして、彼がそれによって生計を維持する場合、 万人に共有されていた知識の一部が創作者に帰属することは自然的権利ということが できる。 一方、ロックは所有権を生存権によって基礎づけているようではあるが、生命・健康・ 自由・私有財産の権利 [67] が並列して主張されるのを見るときに、 私有財産を保有するのは基礎付けを必要としない権利であると認識しているとも考え られる。所有されない財産は 「荒廃する [68]」のであり、 神は地を 「生活の最大の利益と便宜とに資するように利用すべく理性を与え [69]」たとしているからである。 この場合、創作は所有されなければ荒廃するだろうか。 生存権に基礎をおく先の理由付けよりは弱いかもしれないが、おそらく、 ある種の創作、例えば学術的研究は、 それを生み出した創作者自身によって発展されることが望ましいかもしれない。 この場合も創作を所有する根拠の一つとして挙げられるだろう。 しかし、一層強固な根拠としてあげられるのが、「加工の論拠」である。 「何人も自己の一身(person)については所有権(property)を持っている。 これに関しては、 彼以外にだれ一人としてなんらの権利を持たない [70]」そして自分自身の労働 (labour)、手の働き(work of his hands)は、彼のものであるとする。人間は 「自分自身の一身およびその活動すなわち労働の所有者であるが故に、 依然として自分自身のうちに所有権の大きな基礎を持っていた [71]」のである。 「そうして彼自身のものである何物かをそれに付け加えたのであって、 このようにしてそれは彼の所有となるのである [72]」 という部分は人格権説の最も有力な論拠となるだろう。そしてそれによって 「他の人々の共有の権利を排斥する何物かがそれに附加されたのである [73]」。 自己の一身に当然に頭脳も含まれるし、 頭脳による労働というものも考えられるだろう。しかし、 ロックの言葉を厳格に解釈するならば、手の働きによってもたらされる「表現」 に限られ、純粋に頭脳の中の作業である「アイデア」 には拡張されえないかもしれない。 「彼が自分の存在の維持ないし慰安に用いたものの大部分をなすものは、 発明および技術が生活の利便を改良するようになって以来は、 完全に彼の個人のものであり [74]」 という部分は、ロックが発明や技術が生産性を向上することを認めながらも、 その発明を利用して獲得した所有物について発明者の持分を認めていないとも読み取 れる。このことは発明が特許で保護され(国家の承認による独占だから、 所有しているのではない)、著作権においては、 アイデアは保護されないとする考え方と適合している。 さて、ここで検討されねばならないのは、労働がただ為されれば良いのか、 あるいはその人の個性的人格が附加されなればならないのかという問題である。 労働がただ為されるより多く要求されていることは、 「自分の労働によって土地を占有するものは、 人類の共有財産を減少するのではなくてかえって増加するのである [75]」 と主張されることからわかるし、一方、耕作地の所有が認められることから、 (耕作している土地に人格が反映することは考えられるが) 芸術的な意味での個性的人格の附加までは要求されていないと解される。また、 ロックは労働の成果の程度については考慮を加えない [76]。すなわち、 ある領域をAという人物が獲得するよりもBという人物が獲得した方がより多くの収益 を人類にもたらすのであるから、 Aが先占したとしても Bが所有すべきなのであるという功利主義的な議論をしていな い。 この無為より上、個性附加以下の関与を必要するものの、 その内容について優劣を論じないという加工の論拠の基準は、 現在の著作権制度において 「何らかの表現がなされていれば著作権の保護対象となりうる」 とする基準とよく適合する。また、剽窃の場合、時間的先行関係が問題となるのみで、 仮に剽窃した側がいかに素晴らしく題材を表現していた場合でも、 内容の優劣が考慮されないことにも適合する。 以上のように、ロックの自然権から導かれる所有の理論、とくに加工の論拠は、 創作の世界に応用しても適合することが明らかになった。
33.3 所有の限界次にロックの設定した所有権の限界について検討する。ロックは所有権に対する3つの制限を掲げている [77]。(I)人は、 腐敗させずに自分で使用し得るだけのものを所有する権利しか持っていない [78]。というのは、 神は人間に諸物を享受の為に与えたのであるから [79]、とする神学的論拠。(II)人は、 他の人にも十分なものが常に残されている限りで、 物を所有する権利しか持っていない、という明示的ではない論拠。十分に余剰があり、 他者の利用を害することがなければ、 「それは全く何も取らなかったのと同様である [80]」とする部分と、 「他者を害するように行為してはならない」という黙示の規範から導かれる。そして (III)自然状態において、人は、 加工または占有する労働能力が彼に許すだけの物しか所有できない、 という仮構的な論拠 [81]である。 これを頭脳による創作活動に類推するならば、やや困難ではあるが、(Ia) 人はその創作物の価値を引き出しうる期間内でしか所有できない、 と類推できるかもしれない。しかし、創作の成果が文字どおり「腐敗する」 ことがない以上、 無制限の所有が認められないこと以上の論拠としては使用できないだろう。(IIa) これは表現の多様性が大きい芸術作品などについては制限として適合しない。一方、 表現の多様性に限界があるだろう創作には制限となりうる。 特定の目的に向けられた実用作品については表現の多様性が限られるので、 所有が許されない表現も存在することになる。(IIIa)この制限は、 創作にも当然に適合する。 誰も自分の頭脳が生みだせなかった創作物を所有することはできない。 この論理と職務著作の規定は矛盾することになる。しかし、 ロックは使用人の労働によっても所有物を取得しうるとしているので [82]、 ロックの思考体系ではこの矛盾は問題とならなかったようである [83]。 以上検討されたように、ロックの所有権理論からは、 創作の所有権について制限を設けることが困難であることがわかる。また、 何らかの制限を設定することが必要であるとしても、 保護すべき創作物の種類に関する制限についての基準を示しても、 保護すべき期間についての基準は何ら与えてくれない。
33.4 保護期間の時間的制限それでは、ロック自身が、創作に対する創作者の権利を、 永久に存続する所有権類似の権利であると考えていたかというとそうではない。 1662年印刷法を復活させる最後の試みが行われていた1694年に書かれたと思われる、 彼自身による1662年印刷法についての手稿 [84]をみながら、 彼の考える創作に関する権利の時間的制限について検討する。ロックは、1662年印刷法の6条への批判で、 書籍業カンパニーがキケロなどの古典作品について独占権を持っていることを激しく 糾弾している。書籍業カンパニーの独占のために、イギリス国内における古典作品が 「活字、紙質、正確性だけでなく、 様々ある諸版のうちから唯一つの許された版だけが印刷されるという両面で、 ひどく劣悪に印刷されている」とし、また、 海外における優れた改訂版が輸入される場合、理不尽な示談金(composition, 6シリング8ペンス) を書籍業カンパニーが課すために輸入書籍の価格が不当に高額になっていると批判す る[85]。そしてその怒りは 「この法律によって、学者は、これらのラテン語も理解できないような怠惰な “ならず者”たちの権力に従属しなければならないのである。」 という一文によく現れている。 そして続く段落で、「仮に別の印刷に関する法律が作られるべきであるとしても、 すでに50年にわたって印刷されてきた書物に関して、 何らの特別な権利を誰も持つべきでないということは合理的ではない。しかし、 その者と同様に誰もがそれを印刷する権利を持つべきだろう。というのは、 そのような権限[独占的印刷権] によって、それらの書物は「眠って」しまい、 他の人々を妨害して多くの良書を失わせてしまうことになるからである」と、 創作に関して何らかの特殊な権利が存在することを認めながらも、 それ以上にそれらの創作が自由に印刷されるべき事を主張している。 しかし、その主張が古典作品を念頭にしてなされていることは、「現在、 執筆し自分たちの原稿を書籍販売業者に売り払っている著作者たちを考える... 場合を除いて」という限定から理解される。彼の所有権理論では、 人が貨幣を使用した段階で「暗黙かつ自発の同意により.... 不均等な私有財産を作りだす物の配分が.... 実行されるようになった [86]」 とされる。そして、この状態において「法が所有権を規律するのであり、 そうして土地所有は実定制度によって定められることになる [87]」としている。 このように彼は現実の所有権状態は実定法(制度) によって規律されるものであると考えているので、 自己の原稿を売却した著作者たちが、 それでもなお創作について何らかの権限を有するべきであるとは考えていないような のである。 では、売却された原稿(ここでは創作そのもの)が、 どの程度の期間の保護を受けるべきかについて、 ロックはどのように述べているだろうか。彼は、 「現在執筆することによって生活している著者から著作物を獲得した者については、 彼らの所有権を著者の死後の特定の年数、あるいは最初の出版から、例えば、 50〜70 年に限ることは合理的だろう」と手稿の最後の部分で述べている。 この主張の根拠は示されていないので、 いかなる理由によって売却された作品の保護期間が、 創作者の生死と連動されるべきなのかはわからない。 まして出版後50〜70年という期間の根拠も不明である。ただ、 この年数が一般的に考えられている人の寿命と同じ程度であるから、 彼は著作者が死亡すればそれは自由にされるべきであると主張していることがわかる。 ロックが全体として書籍業カンパニーの独占を口を極めて批判していることから、 この年限が彼らの独占を終了させるための目的で設定されていることは明らかである。 したがって、彼の所有権理論と手稿からうかがえる保護期間についての彼の主張は、 次の通りにまとめられる。
34 著作権法の実質 これまでの議論を踏まえて著作権法について考察する。 自然権論に立ち、所有権類似の権利として著作権を捉える限り、 著作権法で与えられる創作者の権利とは、譲渡不能で、 創作者の生命に従属する属人的権利か、 あるいは売却すれば直ちに移転する永久不滅の財産権としてか構成しえない。 そしてロックはそれは後者として理解していた。 しかし、創作者が創作物の対価として貨幣を受け取った瞬間から、 全面的に貨幣による評価を彼が承認したと考えることは、創作者を著しく不利にする。 このことは出版所有権論が証明したところである。 著作権法はこのような創作者の不利益を回避しようとする制度であるから、 貨幣の導入にともなう自然状態からの移行は、従業員としての創作の場合を除き、 国家の政策によって制限されていると見るべきだろう。(職務著作の場合の矛盾は、 すでに見たようにロックの理論では完全に無視されている)また、 著作権を所有権と同様に把握して、 永久の排他権を認めることが公益に反することは前述のロックの激しい批判によって も明らかである。排他的独占権に時間的制限を設ける根拠は、 自然権からは導くことができない。したがって、これもまた公益の観点から、 国家の政策によって制限されていると考えられる。 したがって、著作権法で与えられている創作者の諸利益は、 いずれも特許と同様の実定法上の権利であることを否定することはできない。筆者は、 とくに知的創作の精神的所有から導かれるとする作品公表後の創作者の排他的独占権 が、自然権によって裏付けられているとする説を否定する。 作品公表後の排他的独占権は、 特許と同様に国家によって与えられた実定法上の権利であり、 他の競合する諸利益との政策的衡量を許すのである。
Note
|


|
白田 秀彰 (Shirata Hideaki) 法政大学 社会学部 助教授 (Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences) 法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450) e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp |