 「包括メディア産業法」
への私案
「包括メディア産業法」
への私案 
PART 1
1 はじめに 筆者の主たる研究業績は著作権法の歴史研究であるが、 並行していわゆるサイバースペースにおける法的諸問題についても研究を進めてきた [1]。現在 筆者は、大学において 「情報法」の講義を担当しているため、 さらに広くメディア全般に関する目配せが要求されるに到っている。 対象領域の広さと変化の速さに自身が対応しきれているか心許ないかぎりだ。 そうした浅学の身でありながら、筆者は「メディア産業基本法検討委員会」 のメンバーとして、林 紘一郎 氏の「包括メディア産業法」構想の議論・ 検討に草案段階から参加させていただいた。同構想において示されている「水平分離」 の考え方は、 現在のメディア関連法の錯綜状態を整理するために有益な視座であると考える。 通信と放送の融合、さらにはコンピュータ・ ネットワーク技術の発達にともなう新しいメディアの登場など、 メディア関連法制が難題山積の状態にあるなかで、「通信」と「放送」 をそれぞれ別個に法の枠組みに収める現在のメディア法制を根本的に見直すことが必 要であることは、多くの論者によって指摘される。加えて筆者は、 そうしたメディア法制の再編を構想する際に、 知的財産権制度も視野に入れる必要があると考えている。知的財産制度は、 一般的には内容(content)に関する制度だと見られるが、 通信事業において問題となる通行地役権(right of way) と類似した効果を発揮する制度として考えることもできるからである。 本論の執筆を依頼されたとき、大学での講義内容を充実させるために、通信・ 放送産業の歴史に関する文献を読んでいた。それらは、 『アメリカ電気通信産業発展史』、『英国電気通信事業成立史論』、 『メディアの生成 -- アメリカ・ラジオの動態史』 [2] である。 これらメディア産業の発達史を概観する文献を読み進めているとき、 筆者は継続的な既視感を覚えた。それは、 それらの文献がたどるメディア産業発展の様子(19世紀末から20世紀末まで)が、拙著 『コピーライトの史的展開』[3] で 筆者がたどった出版産業の発展の様子(なかでも16世紀から17世紀末まで) と根本的な部分で類似している、あるいは同一の原理が作用しているのではないか、 と見えたからである。 情報を伝達する産業として、郵便(運輸)、出版、通信、放送産業は、 基本的に同一の機能をはたしている。これを受けて、林 氏は、メディア法制を、 出版モデル(P型)、コモン・キャリア・モデル(C型)、放送モデル(B型) に大別する枠組みを提唱している [4]。 しかしながら、出版産業が後二者に比較して長い伝統をもつため、 その制度には歴史的伝統的な要素が強固に結合している。このためか 林 氏は、 「包括メディア産業法構想」の初期段階で、 出版モデルまでも統合するアイデアを示していたが、まず通信・ 放送分野を統合する構想を提示した。 本論では、林 氏の提示したモデルを批判的に展開し、水平分離された六つの層 (layer)からなる伝送経路モデルを提案する(図1)。また、 伝送経路モデルの各層をソフト部門、ハード部門、 利用者の三つのカテゴリーに整理し、 それぞれの部門および各層間の禁止的権能が均衡するように制度設計すべきことを提 案する(図2)。また、情報流通の流れを制度的に保障するために、 経路へのアクセスとしての「通行地役権」とコンテンツへのアクセスとしての 「著作権」について、また加えて技術支配の保障手段としての「特許」についても、 競争制限的権利行使を抑制する独占禁止法的視点を導入することが必要であることを 提案する。 「包括メディア産業法構想」のような法の大改正を必要とする制度改革については、 現実問題として多くの課題があり、 実現については多くを期待できないと考えるのが一般的な印象だろう。 そういう意味で、「水平分離」 を基礎とした法制度の整備が仮に可能であったとしても長い時間が必要であると考え られる。しかしながら、筆者は、 アメリカにおける電話事業の展開とイギリスにおける電話事業の展開を比較する中で、 次のような考えに到った。 すなわち、(1) 最終的にどのような形態に安定するか不明確なメディアを制度の中に位置付ける場合、 既存の制度を参考にすることはできない。(2) メディアの形態は、 メディア事業者間の競争によってのみ安定形態へと収束していく。ゆえに、(3) 法制度は、メディア事業に「枠」を作るように設定されるべきではなく、 事業者の活発な競争を担保するように設計されるべきである。また、(4) 仮に既存メディアへの規制が、新メディアの事業に影響を及ぼす場合、 不効率な初期条件が設定されてしまうことを避けるために、 既存メディアについても再編成すべきである、というものである。したがって、 コンピュータ・ ネットワーク技術を応用した伝送が初期段階にあると考えられる今こそ、 水平分離を行いメディア産業構造の再編成を行うべきと主張する。 なお、本論に示された私案は、 上述の文献に示された情報伝達の歴史を踏まえたものであるが、 論述が錯綜することを避けるため、本文中では、 具体的にどのような事例をもとにした議論かは脚注のみにおいて示す。また、 本文末に補足として「メディア小史」を示す。
2 水平分離 「メディア」という用語は、本来「媒体」という意味であることは言うまでもないが、 現在の「メディア」という用語は、とても広義に用いられており最広義では、 「著作者」から始まり利用者が直接接する「端末」 までを含む抽象的な伝達システムを指すまでになっている。 そこでまず、図1に示すように、 メディアによって情報が伝達されていく過程を水平分離的に配置したチャートを考え る。すると、著作者(author)→編集者(editor)→伝達者(transmitter)→経路保有者 (channel holder)→端末(terminal)→利用者(user) という一連の流れを想定することができる。これを以下 「伝送経路 (transmission path)」と呼ぶ。
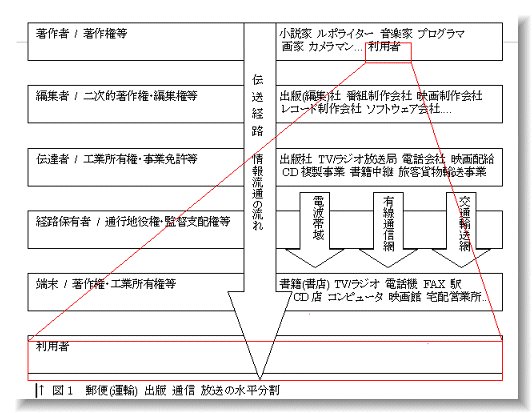
著作者は、他の主体に対する禁止能力として著作権(copyright)等を保有する。 編集者は、同様に二次的著作権(derivative right)および編集権(editorial control) 等を保有する。伝達者は、同様に伝達手段に関する工業所有権 (patent / trade secret)等、あるいは事業免許(license)等を保有する。 経路保有者は、同様に、公的・私的所有権から派生する通行地役権(right of way)、 各種監督支配権(administrative power)等を保有する。端末については、 それが法的に伝達者に帰属するものか、利用者に帰属するものかまちまちであるが、 物理的には利用者に帰属する一方、知的財産権(copyright / patent)等を経由して、 端末を構成する要素の一部が、著作者、編集者、伝達者に帰属することもある。 これら主体が保有する法的権能には、それぞれ複雑な個別の法理が付属しているが、 それら法的権能の分析と相互関連性の検討は、後の課題としたい。しかしながら、 いずれの法的権能についてもそれらの能力が禁止権として用いられる場合、 とくにそれらが絶対的禁止権として用いられる場合、 伝送経路を停止させてしまうことが了解されよう。したがって、禁止権の行使は、 ある主体が他の主体を牽制し、 情報流通の流れから発生する経済的利益の配分を主張するための力(power)である。 さて、図1を大きく眺めると、著作者・編集者は、ソフトウェア部門(以下、 「ソフト部門」)を形成しており、伝送技術・経路・端末は、ハードウェア部門(以下、 「ハード部門」)を形成している。利用者は端末を経由して、ハードを利用し、 ソフトを享受する。端末は、ハード部門の末端であり、 かつ利用者の一部として見ることができる。ここで、 ソフト部門がもつ諸権利を情報支配力(control of information)、 ハード部門がもつ諸権利を経路支配力(control of channel)と総称する。林案では、 図1でいう著作者・編集者部分を「メッセージ(message)」、伝達者を「メディア (media)」、経路を「通行権(right of way)」 と置いて水平分割することを提案している。私見では、林案の水平分割は、 より細分化されるべきであり、また「メッセージ」「メディア」「通行権」 という名称には、より適切な名称を与えるべきであろうと考える(図2)。
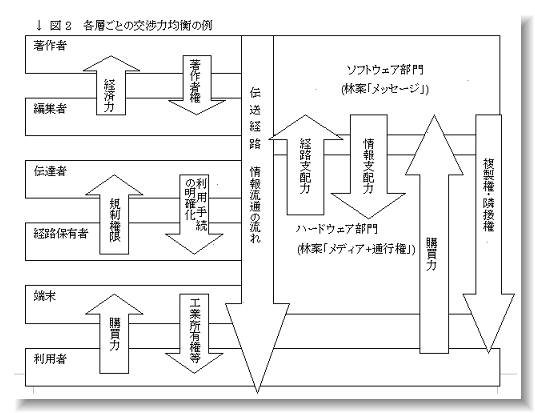
ソフト部門からハード部門をみた場合、 それは自らの持つソフトウェアを利用者に伝達するために用いる資源(resource) である。逆に、ハード部門からソフト部門を見た場合、 それは自らのもつハードを利用者に使用してもらうための資源である。 ソフト部門とハード部門は、 情報の流通において自らの資源を経済取引における交渉力の基礎とすることができる。 すなわち、 ソフト部門はハード部門を牽制するために情報支配力を行使することができ、逆に、 ハード部門はソフト部門に対して経路支配力を行使することができる。 伝送経路において、ソフト部門とハード部門が分離され、 かつ両者の交渉力が均衡している場合、 利用者側が情報の享受において著しく不利な状況におかれることが少ない。 すなわち情報の流通が円滑化されうる。逆に、 両部門のいずれかが突出した禁止能力を発揮する場合、 情報の流通を支配する危険が生じる。したがって、 図1に示された構造が適切なものであるならば、事業の水平分離が必然の前提となり、 なおかつそれら事業を規制する「包括メディア産業法」の主たる目的は、 両部門の諸権利(禁止権)が均衡するように法制度を調整することになると考える。 さらに、ソフト部門を規制する事業法においては、 著作者と編集者の交渉力を調整することが主たる目的となる。すなわち、 著作権を中心とした知的財産権の再構築(restructuring)が課題となろう。現在、 知的財産権制度の強化が進んでいる。それは、 現在の知的財産権制度の枠を維持したまま、 権利者の禁止権を強化することを意味しているように見える。しかし、 伝送経路全体を視野にいれれば、 禁止権の強化が直接的に情報産業の強化に結びつくものでないことが理解されよう。 同様に、ハード部門を規制する事業法においては、伝達者、経路保有者、 端末に関する権利保有者の三者の交渉力を調整することが主たる目的となる。 高度な情報技術が情報伝達にもちいられる現在においては、 送信側たる伝達者と受信側たる端末が同一系列の技術によって統合される場面が多く みられる。すると、 技術力や工業所有権等によって端末まで支配する伝達者と経路保持者および利用者間 の交渉力を均衡させることが必要になるだろう(図2)。
3 伝送経路要素のモジュール化 現在のメディア産業法は、いわゆる「メディアの種類」 によって区分けされ法的規制を受けている。これは、林 氏が示す、 四類型によって示される。すなわち、出版モデル(P型)、コモン・キャリア・モデル (C型)、放送モデル(B型)、データ処理モデル(D型)である。 この林 氏の四類型は情報を運ぶ手段(conduit)と、運ばれる内容(content) にかかる法的規制のマトリクスによって導かれた概念形であるため、 現在の法制度を整理する上で有用なものといえる。 しかし、図1に示された伝送経路を考慮すると、この四類型には欠陥があるといえる。 第一に、すべてのモデルについて、 著作権が根本的な禁止能力として関わることが見えにくくなっている。第二に、 これらモデルの名称が、 それぞれの事業形態を代表していることを示しているわけだが、別々の層(layer) の概念が混在しているため、問題の所在が見えにくく、 結果的に既存の法制度の枠を前提してしまっている。第三に、 第二の欠点の反映として、D型と仮称されている「データ処理モデル」 にどのような規制枠を設定すべきかが不明になっている。林 氏は、D型について 「規制が存在しないので、基本的に P型「出版モデル」に準ずる」 としているが [5]、それは、 D型に現在のところ規制がかかっていないことを示しているにとどまる。 ただし、林 氏は、D型に対する規制への考察をすすめ、D型に対して、 経済的規制が存在しないが社会的規制がかかるモデルを構想し「電子公衆送信法案」 と称する法案まで作成している [6]。 この「電子公衆送信法案」において、林 氏は、 D型の情報伝達技術の性質を正しく踏まえ、「通信」の部分集合として「放送」 を位置付けるのではなく「放送」の部分集合として「通信」を位置付けた。この点は、 とくに画期的かつ重要である。というのは、「通信」から「放送」 という事業形態が現われたのは、 技術発展史の偶然であり [7]、 情報伝送過程を抽象的に考察すれば、相手方を特定して情報を発信する「通信」 のほうが、相手方を特定せず発信する「放送」 よりも特殊な場合であるといえるからである まず、四類型に対する第二の批判点から解説し、第三の批判点への私見を示す。 第一の批判点については、次節において、 経路保有者がもつ通行地役権と著作権を比較するなかで明らかにされる。 図1を参照すると、著作者から利用者まで、六つの層がある。P型事業は、 著作者から端末までを強く垂直統合した事業である。すなわち、著作者(著作者) →出版社(編集者・伝達者)→書籍中継(経路保有者)→書店(端末)である。C型事業は、 層モデルのうち伝達内容にかかわらず、伝達者・経路保有者・ 端末を支配している事業者のことを指し、垂直統合性は低い。B型事業は、 放送番組製作(著作者・編集者)→放送局(編集者・伝達者)→電波帯域(経路保有者) までを強く垂直統合した事業である。すると四類型のマトリクスは、 次元の異なる事業をおなじ平面上で比較しようとするものであるといえる。 ここで、図1の各層を縦に繋ぐ線を考えると、 それぞれの層の要素が垂直的に結合する必然性がないことがわかる。 小説家が書いた作品は、俳優等が朗読したものを録音し、 CD販売経路で利用者に届けられてもよいし、手紙の送り主は、 自らの手紙を貨物輸送業者に託して、届けてもらっても良いはずである。事実、 そうした事業は主流とは言えないまでも実際に行われている。 現在生じている、「通信と放送の融合」という現象は、 実は伝達者と経路が水平分離し、無線(電波)と有線(管路) との間で相互に乗り入れはじめた現象に他ならない。すると、 「郵便事業の民営化と一般家庭向け軽貨物事業の郵便事業参入」 も同じ現象の違った様相であると見ることができる。同様に、「電子出版」 「電子音楽配信」「音楽専門(有線・無線・衛星)放送」なども考えることができる。 すなわち、それら新・ 情報流通産業を一つのカテゴリーとして把握することは意味を持たないし、まして、 それらに共通して効率的に作用する法制度を構築することは不可能であるとみるのが 妥当だろう。 すなわち四類型で仮にD型に集められていた諸産業類型への規制枠を考えるというこ とは、既存の情報流通産業を水平分離し、それらが保有する法的権能(禁止能力) を伝送経路のなかで均衡配分するという「包括メディア産業法」 のアイデアそのものを指すことになるのである。 これが先の第三の批判点に対応する私見である。 われわれが出版、通信、放送という三つの情報流通モデルに拘束されていた理由は、 歴史的なものである。そのパターンは、以下の通りである。(1) ある技術をもとに様々な形態のビジネス・モデルが発生する。(2)それらのビジネス・ モデル間の競争のうち、ある形態が勝ち残る(この場合、 ある技術を発明し特許を保有する事業者がもっとも有利な立場にたつ)。(3) ある形態のビジネスは特許を基礎に市場支配力を発揮し独占(寡占)状態に移行する。 (4) この独占状態に対して、政府からの規制・介入が行われる(この場合、 政府は経路保有者として通行地役権、監督支配権を用いる)。(5) 規制枠組が確定し、 法制度が整備される。(6) ビジネス・モデルは法制度に拘束され固定化される。 われわれが所与としてきた出版、通信、放送という枠組みは、いずれも(5)、(6) の過程の段階でたまたま勝ち残っていたビジネス・ モデルが制度的に固定化されたものである。 この歴史的検討については、参考資料として本論につづく「メディア小史」 を参照願いたい。
4 制度設計の要点 「ある情報技術」→「ある事業形態」に進む過程には、法的要素が二つ、 あるいは三つかかわってくる。 まず、技術に対する発明特許がどの程度強力に保護されるかによって、 事業の初期条件がほぼ決定される [8]。 技術に関する理解が深くかつ開発能力に長けた主体は、多くの場合、 発明者であることが多いと推測されるから、発明特許制度は意義のある制度である。 しかし、このとき発明者がある種のビジネス・モデルに固執すると、 技術の事業化は失敗する可能性が高くなる。また、 技術の初期段階で技術に関する理解に乏しく、開発能力にも欠けた主体、 たとえば公的主体が、通行地役権、監督支配権等を用いて事業を接収してしまうと、 技術の事業化は失敗する可能性が非常に高くなる (ただし、後の「第二の発明」 がおこなれ、技術に適したビジネス・モデルが発見された後であれば、 国有化等の公的独占政策もそれほど悪い結果をもたらさない)。 つづいて、特許によって保護された期間に技術の応用化について様々な実験が行われ、 ある技術について、その社会・経済的条件下において適したビジネス・ モデルが発見されると(以下「第二の発明」)、その技術は成功し、多くの場合、 特許による独占のみならず、市場支配力によって事実上の独占が生じる。 この段階にいたれば、独占から発生する弊害を抑制・除去するために公的主体が介入・ 規制することが必要になる。このとき、公的主体は、通行地役権、 監督支配権等を用いて事業者の支配を試みる。というのは、図1でも明らかなように、 この部分の資源はボトルネックになっているからである。こうして、公的主体の活動、 すなわち立法活動を通じて、関連法規、監督官庁等が整備される。 すると法や制度の硬直性が、技術の枝わかれ的な発展を抑制し、 法が想定した事業形態へと事業者を拘束する結果となる。 ここで注意しなければならないことは、経路保持者以外の主体については、 伝送事業者(伝達者を中心として端末までを含む主体とする)との間で交渉する余地、 あるいはせざる得ない状況があるのに対して、経路保持者は、 絶対的な支配力を保有していることである。経路保持者以外の主体の場合、 伝送事業者の提案を完全に拒絶した場合、 みずからが保有する資源の潜在的な市場へのアクセスを失うことになる。 したがって合理的な主体であれば交渉に参加するため、 交渉によって伝送事業者と妥協することが可能である。しかしながら、経路保持者は、 もともと市場へのアクセスについての興味に乏しく、 かつ自らが保有している通行地役権あるいは電波帯域(right of way / wave band) という潜在的資産については課税されていないため、 活用しないまま死蔵することも厭わない。 公的主体が保有するものならなおさらである [9]。ここで、通行地役権は、 決定的な力として伝送事業者にかかわってくる。ゆえに、 林 氏がとくに通行地役権に着目し、もっとも基礎的な法として「通行権法 (right-of-way law)」を唱えた [10] ことは、合理的である。 そして、現在生じつつあるもう一つの絶対的な力についても検討する必要がある。 それは、現在までの歴史的経緯から、 いくつかの情報流通経路が垂直的に統合されていることから生じる。 出版モデルの事業と放送モデルの事業については、 コンテンツの確保から利用者までのアクセスが垂直的に完成している。すると、 これらの事業者と垂直的に統合されている著作者・編集者たちが保有する著作権、 二次的著作権、編集権が絶対権として機能するようになる。 著作者・編集者たちは、 すでに既存の流通経路をもちいて市場へのアクセスが可能である。すると、彼らは、 新しい形態の伝送事業者に対して、 経路保有者が保有する通行地役権と同じ戦略が取れることになる。 新しい形態の伝送事業者が情報流通事業に参入してきた場合、 流すべきコンテンツが必要不可欠になる。仮に自前のコンテンツを整備できない場合、 著作者・編集者たちと交渉することになる。ところが、著作者・編集者たちは、 すでに既存の経路を保持しているので、交渉を拒絶しうる。こうして、著作権等は、 新規伝送事業者に対して絶対的な力となりうる。 この場合、二つの可能性がある。一つは、著作者・ 編集者が既存伝送事業者と強固に統合されており、 かつ新規伝送事業者が既存伝送事業者に対して脅威となりうる場合、 新規伝送事業を市場から排除するために、著作権等を用いることができる。仮に、 新規伝送事業が、既存伝送事業よりも社会的コストの低い事業であった場合、 社会的損失が生じることになる。 とくに既存伝送事業が過去におこなった事業への投資、すなわち埋没費用(sunk cost) が大きい場合、新規伝送事業を排除しようとする動機が大きくなる。 もう一つは、先の条件のもと、既存伝送事業者が、新規伝送事業を有望であると考え、 その新規伝送事業に支配力を行使する場合である。仮に、新規伝送事業が、 まだ技術的揺籃期にあり、適切なビジネス・モデルの発見すなわち「第二の発明」 を達成していない場合、既存事業者の影響力によって、新規伝送事業が、 既存事業の枠内あるいは亜流のビジネスとして非効率に固定化される可能性が生じる ことになる。技術的可能性からビジネス・モデルを模索するのではなく、ビジネス・ モデルに合わせて技術的可能性を制約・ 誘導するという動機が大きくなる [11]。 このように考えれば、新規伝送事業の成功が困難な制度的理由が明らかになる。 垂直統合構造が残っているからである。垂直統合を制度的に解体し、 水平分離を導入すれば、 著作権等が伝送事業の絶対的な制約条件とならなくなることに加え、 情報流通事業間でビジネス・モデル競争が生じ、 もっとも効率的な情報流通環境が整備されるであろう。これは、 情報流通に必要な社会的費用を低下させるという点でも合理的なことである。また、 水平分離案は、ソフト部門の法制度に直接影響を及ぼさない。
5 まとめ 結論すれば、まず現在の郵便(運輸)、出版、通信、 放送という伝送事業の垂直統合を水平分離してモジュール化する、「一般伝送事業法 (general transmission law)」を構想することが望ましい。一般伝送事業法では、(1) 事業におけるソフト部門、ハード部門の垂直統合の制限、(2) ソフト部門とハード部門のそれぞれについて、 競争排除的な事業形態を禁ずる独占禁止法的な仕組みを導入することが必要となろう。 ついでソフト部門、すなわち著作者と編集者の間の権利調整法として、 労働法的要素も含んで著作者の権利を保障するような、「著作者権(authors' right) 法」の再構築が必要となろう。ソフト部門と利用者との間は、複製法(copyright) として現在の著作権財産権および隣接権を中心として不正競争防止法的に構築する方 が合理的と考える。あるいは、これらを一括して、「情報内容法 (information content law)」とすることも考えうる。 さらにハード部門、すなわち、伝達者、経路保持者、端末の権利調整法として、 通行地役権、電波使用免許、運送事業免許等を規定する法が必要となるだろう。まず、 経路保有者が絶対的な禁止権を行使できないように、 彼らが享受する権利の性質の設計を綿密に行う必要がある。税の導入等によって、 それら経路を非効率に占有する経路保有者に、 効率的利用のインセンティヴを導入する等が考えられる。また、 経路を利用する伝達者が それら経路の使用権を取得する手続を、 一つの原則に基づいて明確化することが望ましい。これらを一括して、「伝送路権法 (transmission path law)」とすることも考えうる。また、 伝送技術関連の知的財産権が、 競争排除的に用いられないようにするための制度設計も必要となろう。たとえば、 伝送者が端末までを排他的に支配することについて、 なんらの規制手段も存在しないのでは、 伝送技術の発展可能性が制約されてしまう可能性がある。 とくに多数の技術が連携して機能する現代においては、 伝達経路に関与するさまざまな事業者の相互接続性を保障するような制度設計が不可 欠と考える。 情報通信革命、流通革命といわれる現在、 古い制度的枠組みが非効率な事業形態を保護するような状況が発生しているのではな いかと懸念される。いま、情報通信関連法における制度改革で必要なのは、 競争制限的な制度の解体と、事業間競争を促進するような制度枠組みの設計である。 本論で示した私案が何らかの参考になれば幸いである。
Note
|
PART 2メディア小史
1 印刷・出版 印刷術は、既存の(筆)写本の大量生産技術として15世紀半ばに開発された。これは、 写本というメディアに倣った形態のビジネスとして構想された。このため、 初期の印刷本(incunabula)は、できるかぎり写本に似せて、頭文字書き (rubrication)、欄外装飾(illumination)、革装(binding) を行っていた [1]。グーテンベルグ (Johannes Gutenberg)の「42行聖書」は、初期印刷技術の嚆矢であるだけでなく、 印刷術による写本の再現の典型的な例である。これらの装飾は、 職人による手工業によって行われたため、 印刷術によるコスト低減効果を縮減することになる。 印刷術が文字による情報伝達のコストを劇的に下げる可能性をもつことは了解されて いただろうが、大量の印刷物を受け入れる大衆的市場が存在しないことから、 既存の写本市場が狙われたのである。 写本の代用品としての印刷本が印刷技術独自の地位を確立したのは、 16世紀初頭のアルドゥス・マヌティウス(Aldus Manutius)によるギリシャ・ ラテン古典の出版事業である。彼は、中世写本(ゴチック体)を模倣することなく、 グリーク体、ローマン体、イタリック体の活字を独自にデザインし、 新しいタイポグラフィの世界を提示した。また、 古典作品を学問的に校訂し小さな版形で大量に印刷することで、 欧州全体に市場を拡大することに成功した [2]。 それまでのゴチック体は、筆写生が書体を統一しやすいように工夫されたもので、 活字がゴチック体を採用する必然はなかった。アルドゥスは、 石碑や建築物に刻まれることを目的に発達したローマン体(大文字) を紙面に移すことで、写本の呪縛から逃れたのである。また、 写本は手で書き写すため、文字が大きく、このため写本は、 ある程度の大きさの版形である必要があった。しかし、 印刷であれば目で認識できる大きさの文字を 小さな版面に詰め込むことができる。 こうしてアルドゥス以降、本は写本から独立したメディアとなり得たのである。 大量印刷という印刷術ならではの性質が発揮されるのは、印刷業の場合、 19世紀半ば以降である。この時、印刷事業は、新聞の大量発行によりマス・ メディアを形成し、ペーパーバックの印刷によって大衆購読者層を開拓した。本来、 印刷術がもっていた潜在的能力は、 400年かかって開花したのである [3]。 このとき、社会に行き渡った印刷物からは、 写本がもっていた美術工芸品としての要素が、ほとんど削ぎ落とされていたのである。 書籍出版業の事業形態の形成については以下のようにまとめられる。筆写生 (textwriter)もまた、教会・修道院、大学に帰属しており、 都市に存在する文字に関する職能者は、 代書人 (writers of court-hand / writers of text-hand)であり、 それとは独立して装飾職人(illuminators)がおり、さらに独立して製本職人 (book-binders)が存在していた。書籍販売は、文具などを扱う文具商(stationers) による店頭販売か、地方へ雑貨などを輸送していた行商人(hawkers) によって行われた。イギリスでは、15世紀初頭(まだ印刷術は未導入)、 代書人と装飾職人が一体の職能集団として編成され、さらに製本・ 店頭販売までが統合されて、15世紀の半ばには書籍製造販売業者(stationers) として一体の職能集団となっていた。ここに大陸から印刷術が導入され、 新入の印刷業者(printers)は、書籍業組合(stationers' company)に組み込まれる。 すなわち、印刷術が登場したときには、 すでに産業の垂直統合が既存の枠として存在していたのである [4]。著作者は、ギリシャ・ ローマ時代の作家であるか、当時の著作者であれば、教会・修道院、 大学等の研究者が大半であり、当然、書籍出版業に統合されていなかった。 書籍出版に依存する著作者が登場するのは、 18世紀に入ってからである [5]。 こうした、垂直統合の事業形態は、制度的にも強化された。とくに検閲の必要性から、 垂直的に統合された情報流通の流れを監督する単一の代表(責任)機関が設定された。 この単一の代表機関は、書籍業の場合、書籍業組合(stationers' company)であり、 国王勅許により書籍印刷事業に関する排他的独占権を付与された。 すなわち書籍流通経路に関する通行地役権(right of way)類似の権能、 あるいは行政的権能(administrative power) が包括的に書籍業組合に付与されたことになる(規制下の独占)。書籍業組合は、 安定的に収益を挙げられる聖書・暦・教科書の出版権を独占保有する一方、株式 (stock)として組合員間では分散保有し (通信事業における長距離基幹回線に比喩しうる)、 それぞれの組合員出版事業者に対して、個別作品の排他的出版権を保障した (通信事業における地域フランチャイズに比喩しうる) [6]。これらの排他的独占権が、 後に著作権(copyright)と呼ばれるようになるのである。この垂直統合のイメージは、 強固であり、新聞、音楽出版、音楽レコード事業は、出版事業モデルを踏襲した。 本屋、新聞屋、楽譜屋、 レコード屋がそれぞれ独立した専門店として形成されたのには、 こうした歴史的背景がある。 この歴史的事情から、出版事業については、ビジネス・ モデル間競争がほとんど生じなかった。たとえば、 書籍出版業と新聞業が競合した時期があったり、18世紀のイギリスや、 19世紀のアメリカで新しい出版事業形態が試みられたこともあった [7]。しかし結果的には、 長い伝統を持ち、 制度的にも安定していた既存の事業形態を凌駕することができなかった。それは、 出版業の要である著作権制度が既存の事業構造を前提としていたからである。 余談だが、エジソン(Thomas Alva Edison)とバーリナー(Emile Berliner) が蓄音機を開発した当時、蓄音機には録音機能が備わっていたものがあり、 声による筆記が行われていた。この当時の図書館学の記事に(出典は失念)、 「音声の記録による筆記で、著作者その人の「語り」 を記録することができるようになった。この素晴らしい技術は、 今後も発展するであろう。将来の図書館には紙の本は存在せず、 たくさんのレコードが収蔵されることになるであろう。」旨の記述をみたことがある。 技術の成熟形態を予測することの困難を想起させる記述である。
2 通信 通信の方法には、トーキング・ドラムのように音声を利用するもの、 狼煙や腕木信号等の視覚を利用するもの、など様々なものがあるが、 複雑な内容を伝える通信の基本形態は、メッセージを伝達する記号を何らかの媒体 (有体物)に固定し、これを使者に託して宛先に届させるものだと言える。 古代エジプト第12王朝時代すでに職業として手紙を運搬する人物がいたらしい。 手紙は「物」であったので、郵便事業は、 基本的に貨物輸送事業の一種として把握された。人、馬車、 鉄道をつかって郵便事業は貨物事業と一体となって拡大した。 通信事業を制度的にみるとき、「コモン・キャリア (公共運送人)」 と呼ぶ理由はここにある。さらに、 初期の新聞事業が郵便事業と渾然としていたことも指摘したい。 個人的にやり取りされる手紙から、特定の加入者にむけて定期的に送られるニューズ・ レター、街頭でも販売される新聞(小冊子)への展開は直線的なものである。 しかしながら、社会的影響力の大きさから、 あるいは印刷機を用いているという技術的類似性から、新聞は、 書籍と同一の検閲制度の下に置かれ、 郵便事業と分離することになったのである [8]。 郵便制度が公的事業として今日の形態をとるようになったのは、 17世紀から19世紀のイギリスにおいてである。1832年に、ヒル (Rowland Hill) が近代郵便制度の基本型を完成させたといわれる。 最近まで郵便事業が貨物輸送事業の一種として把握されていたことは、アメリカでは、 鉄道事業を中心に規制していた独立行政委員会 州際通商委員会 (Interstate Commerce Commission、以下「ICC」)に、 郵便事業が 1934年まで監理されていたことが端的に示している [9]。 1829年にロシアのシリング(P. L. B. Schilling)が電信技術の実用化に成功し、 1837年にモース (Samuel Finley Bresse Morse) がモールス信号体系を考案することによって、 電信技術は1845年にアメリカで事業化された。マルコーニ (Guglielmo Marconi) 以前の電気通信は、有線でおこなわれていた。では、 この電信線はどのように拡大されたか。基本的に、 貨物輸送に用いられた経路に沿う形で展開された。たとえば、幹線道路沿い、 鉄道沿い、海外航路下の海底である。事業主体も、 民営で進められたアメリカの事例を除けば、基本的に、(公的) 郵便事業を行っていた事業体によって展開された。 メッセージの伝達は貨物輸送の一種だったからである。 また、そうならざる得ない法的理由があった。 電柱や地下管路に通信線を施設するためには、 公的私的に所有されている不動産を通過する必要がある。すると、 通行地役権 (right of way / wayleaveともいう) を確保しなければならない制度的制約が生じる。後述するイギリスの事例をみれば、 この通行地役権獲得・ 使用料支払いがいかに通信事業について大きなコストとなったかが了解できる。 それゆえ、すでに貨物輸送事業によって、通行地役権を確保していた事業体、 あるいは法制度的に通行地役権使用コストを免除される特権を獲得していた公的事業 体が、電信事業をおこなう結果になるのは明らかである。 新規参入者であるモースが電信事業を立ちあげられたのは、 アメリカならではの地理的・ 制度的事情があった [10]。 仮に有線電気通信ではなく無線電気通信が先に発明されていたならば、 電気通信事業の主体も規制官庁も現在の形態でなかった可能性が高い。 通行地役権の確保が必要なければ、 純粋に無線通信技術の優れた主体が勝ち残ったであろうし、 空間をこえてメッセージを伝達する事業の監督が、 貨物輸送を監督する公的主体である必然性もないからである。 さて、19世紀の半ばから開始された電信事業は、直ちに巨大産業となり、 電話事業がこれを凌駕する20世紀初頭まで成長を続けた。 急速に巨大産業になったことにも技術的・経済的理由がある。鉄道事業とおなじく、 設備産業である通信事業は、初期に莫大な資本投下を必要とするからである。 電信技術が立ち上がった時代、巨額の資本の必要性に応えられたのは、国家、 金融資本、鉄道資本くらいなのではなかったか。すると投資を募る事業計画において、 電信という事業を説明する場合、 貨物輸送との比喩を用いるのがもっとも説得的ということになる。そうであるなら、 事業の所有者たちが電信事業が輸送事業の一種として考えたことに不思議はない。 急速に拡大する通信取扱量の増大は、 一回線一メッセージという技術的制約を乗り越える新技術を求めていた。解決策は、 周波数分割による多重伝送だった。 まだ電気的な周波数分割フィルタが存在していなかったので、 音叉を用いた方法が用いられた。電信で音の階調が伝送できることが明らかになれば、 音声伝送の発明まで、あとわずかの段階に入ったといえる。しかしながら、 電信事業は、音声の伝送については興味を示さなかった。3つの符号(トン、ツー、 無音)でメッセージを送ることのできる電信に対して、 音声によるメッセージ伝送は冗長であり無駄であると考えたのだ [11]。この電信事業者の合理主義は、 ビジネスの道具としての電気通信市場しか見ていなかった。後に発生する巨大な 「ひろい意味での交際」 としての電気通信市場を想像できなかったのだ [12]。 電話は、発明当時には、実用品ではなく娯楽の道具として扱われていた。 利用者と劇場やコンサート・ホールを専用回線で結んだものや、 コインを投下して音楽やニュース番組を楽しむような使用法が存在した。 事業として定着したものもあった。 オーストリア=ハンガリー帝国の首都ブダペストで 1893年に事業開始された 「テレフォン・ヒルモンド」である。これは、 ニュースや音楽を電話回線で流すサービスであった。1900年には、 加入者が6437世帯あり、当時の電話加入世帯のほぼ100%を占めていたという。しかも、 1900年頃、すでに番組を編成し計画的に「放送」を行っていた。 ラジオ放送が ここまでの放送体制を整えるのは 1930年代頃のことである。 テレフォン・ヒルモンドは第一次世界大戦によって壊滅的な打撃をうけ、 1925年にハンガリー・ラジオ放送に吸収されてしまう。また同様のシステムは、 アメリカにも一時的に存在し、旧ソ連では40年間にわたってラジオを上回るマス・ メディアとして機能していたという。このことからもわかるように、 電話にはラジオと同じような「放送メディア」 の可能性もあったのである [13]。
2.1 アメリカにおける展開アメリカにおける電話事業の初期条件は、特許制度によって確定した。 ベルの電話基本特許は、 印刷術の節で説明した書籍業組合への印刷技術の排他的独占権の付与 (国王勅許状と特許制度は、 いずれも patent / letter patentという同一のものであったことに注意) と同一の効果を発揮した。ベル (Alexander Graham Bell)が特許を申請する以前の1875年に、 すでにベルの発明に関するベル特許連合体(Bell Patent Association; 以下ベル基本特許を中心とする電話事業体を「ベル・グループ」と総称)が、ベル、 皮革商人サンダース(Thomas sanders)、ベルの義父ヒューバード (Gardiner Green Hubbard) によって締結されている [14]。 1876年にベル・グループは、電信事業大手のWestern Union社(以下「WU」) に電話特許の購入を持ち掛けるが拒絶される [15]。こうして、電話事業はベル・ グループ、実質的にはヒューバードによって運営されることになる。 ベルの電話市場における独占は、 電話事業の初期において約600件の訴訟を勝ち抜くことで確立された。 なかでも重要なものがWUと争ったダウド事件 [16]である。 電話事業の隆盛をみたWUは、もう一人の電話発明者グレイ(Elisha Gray) の発明を基礎にして、American Speaking Telephone社(以下「AST」)を設立した。 これをうけてNational Bell Telephone社がASTを特許権侵害で訴えた事件である。 この事件ではWU側の弁護士がベルの基本特許が動かしがたいことを確認し、 WUは和解交渉に入る。そこで提示された条件が、(1)ASTは、 ベル特許の優先権を認める、(2) 同社は電話事業を放棄して伝新事業に専念するかわりに、 ベル社も電信事業には進出しないことに同意する、(3) ASTの電話システムをベル社が買い取る、(4) ベル社は今後17年間にわたって、 電話賃貸料と特許料の収入の20%をWU側に支払う、 というものである [17]。(2)(3) の条件は、電気通信大手同士の市場分割協定であり、(1)(4)の条件は、 17年間という特許保護期間と同一の年限から判断して、 ベル側がWU側に支払う暗黙の特許使用料であるとみることができる。 この1879年のベルとWUの市場分割協定によって、 ベル社はアメリカにおける電話事業の独占権を確立したことになる。 電話事業の独占権を確立したベル・グループは、特許保有会社かつ持株会社として、 ボストン金融団からの資本注入をうけながら、順調に事業を拡大する。ベル・ グループは、1881年に電話機の製造を独占する目的でWEを買収、 1885年に長距離電話事業を独占する目的でAT&Tを設立、電話関連技術・ 特許の支配を目的としてベル研究所を設立する。ベル・グループは、 特許を武器に電話事業を地方毎にフランチャイズする戦略をとった。 これにはアメリカの規制枠組みが影響している。アメリカでは、州内通商は、 各州が設置する公益事業委員会の規制下に入ることになっていたが、州間通商は、 連邦政府が規制するものとされていた。1890年代の電話事業のほとんどが州内通話 (州間通信は電信が主として用いられていた)であったため、 規制当局の単位にあわせて事業化する必要があったのだ [18]。また、ベル・グループは、 利用者用端末である電話機をリースするという周到な経営方法を採用した。 これによって、電話機、回線、 交換機の製造から流通までを完全にコントロールする垂直統合を完成したわけである [19]。このように、 われわれが電話事業としてイメージするビジネス・モデルは、特許を中心としたベル・ グループの垂直統合戦略によって作られたモデルに規定されていることが了解されよ う。ベル電話基本特許が電話事業それ自体の独占につながらなければ、 電話事業は早いうちから、研究開発、機器製造、長距離通信、市内通信と、 それぞれ別の事業体によって運営されていた可能性もあるのである。
2.2 イギリスにおける展開アメリカでは、特許が強力な産業構造規定力を発揮したが、イギリスでは、 通行地役権が電話事業の形態を決定することになった。イギリスの場合、 通行地役権が、民間電話事業を牽制する手段としてもっぱら使われることで、 電話事業は大きく立ち後れた。 最終的には通行地役権を道具として電話事業国有化へと進むのである [20]。イギリスの電信事業の免許および国家独占の権限が、逓信大臣 (the Postmaster-General)に付与された法的根拠は、 1868年および1869年の電信法によっている。 電信事業取得の権能ならび電信会社免許の権限が付与され(1868年電信法)、 さらに逓信大臣の電信事業買収の権限が拡大され、 いくつかの例外はあったものの内国電信の独占が、逓信大臣に付与されたのである (1869年電信法)。1863年電信法によれば、「電信」とは 「電信による通信のために用いられる電信線であり、...また、 電信による通信の目的をもってこれに接続使用される機器の一切を意味する」。 1869年電信法では、これに加えて 「電気的信号を介してメッセージその他の通信伝達のために用いる一切の装置」 が含まれることになった。さらに1870年以降、1949年にいたる電信法によって、 同大臣の権限は引き続き拡大された。電信事業の国有化への動きは、 逓信大臣に電信事業の独占権を与えた方が望ましい、 とする見方を反映したものであった。 逓信大臣による電信独占によって電信サービスの改善、 とくに料金の値下げと事業地域の拡大が大幅に進んだという [21]。 こうした逓信大臣による電信事業独占は、 新規事業とくに情報関連事業について排他的独占権を付与するイギリスの伝統に従っ たもので、機能的には、印刷業において書籍業組合が取得した勅許と同じ物である。 逓信大臣には、既存の電信事業の買上げの義務と、 独占範囲内の電信業務に関する免許交付の権限が付与された。また、 電信事業の国家への移管にともなって、 電信会社や鉄道会社の施設を取得した場合の補償が行われた。 電信会社や鉄道会社の施設を取得した場合には、営業権の補償を、 鉄道会社の場合には、会社の所有施設に関わる通行地役権(wayleave) を補償することとされていた [22]。 この通行地役権の支払が、 公共サービスを理由として政策的に値下げされた電信料金 [23]と相俟って、 電信事業を圧迫することになる。 1868年電信法によって、英国内鉄道の大部分におよぶ一般的な通行地役権が、 逓信大臣に付与された。1878年電信法では、 1878年1月1日以降に認可された鉄道については、 無償の通行地役権が確保されるべきことが定められていた。1868年法では、 鉄道会社の資産(不動産)内において、 電信会社が電信線を保有する権利が認められていた。それ以外の民間資産については、 公道沿いの境界や沿道を別とすれば、 逓信大臣には通行地役権は実質なにも認められていなかった。1908年電信法で、 民間資産内の樹木が沿道沿いにある電信線の障害となる場合に、 一定の条件のもとに伐採することができる権能が与えられた程度であった [24]。 ベルの電話特許は、イギリスにおいてはアメリカにおける特許と同年、 1876年12月に取得された。翌1877年7月、エジソンは、 独自に開発したカーボン式電話機の特許を取得する。イギリスでは、 ベル電話とエジソン電話は別個の発明とみなされた。 1878年6月 Bell Telephone Company Limited in London が設立される。 翌1879年8月には、Edison Telephone Company of London が設立される。 両者はイギリスにおける電話事業で競争したが、 アメリカでのダウド事件和解による電話事業のベル・グループへの移管に伴ってか、 イギリスにおいても1880年に両電話会社は合併し、United Telephone Company (以下 「UTC」) となる。これによってイギリスにおいても実質的に電話事業はベル・ グループの海外関連会社であるUTCの独占下にはいることになる [25]。イギリスでは、 電話事業は外国資本の民間企業によって運営される事業であった。 イギリスにおいて電話事業が抑圧された背景には、保守主義の影響がうかがわれる。 1880年代ころから、電話事業の商業的展開が活発化するようになる。にもかかわらず、 電信事業に莫大な投資をしたうえに赤字経営に陥っていた官営電信事業は、 電信事業の延命、すなわち電話事業の抑制に政治的・法的手段をもちいるようになる。 イギリス政府側は、 UTCによる電話事業が逓信大臣の電信事業へ付与された排他的独占権を侵害するもの であるとしてUTCを提訴したのである。1880年11月29日の高等法院 (High Court of Justice)判決では、(1) 電話会社の有する電話線は、 1869年法他でいう意味での電信であり、 こうした電話線や器具を用いて送信されたメッセージは、 同法で言う意味の電信である、(2) 民間企業がそうした電話線や器具を用いてメッセージを送信したり、 受信したりすることは、 1869年法第4状で規定する逓信大臣のもつ特権を侵すことになる、 という主張を受け入れ、1863年電信法における「電信」の定義を拡張し、 電気的信号を介してメッセージその他の通信伝達のために用いられる一切の装置を含 むものとしてしまった [26]。 UTCはこの判決をうけて逓信大臣の電話事業に対する権限を受け入れ、 電話事業からあがる総収入の10%を支払うことで、免許を受けることを選択した。 これは、電話事業が電信事業に対して補助金を支払うことに等しく、 イギリスの電話事業の展開を遅らせる結果となる。「この1880年判決以降、 政府が採用した電気通信政策の基本は、 電信収入の保護というあらぬ願望に固執しつづけ、 あらゆる策を弄しつつ電話システムの発展を阻害する方向に向けられた」 と総括されている [27]。 かくして逓信大臣は、電話事業の排他的権利を有することとなったが、 電話という新しくかつ不安のともなう事業を直接手がける意志もなく、 それができるほどの技術能力も持ちあわせなかったので、 幾多の民間会社に免許を交付した。その際、業者ごとに具体的に事業地域を限定し、 総収入の10%を免許料として政府に納入させるという条件が付された。さらに、 こうした免許の期限は1911年までとされた [28]。1911年に免許がどうなるのか、 何も示されていなかったが、電信国有化という前例から、 政府によって電話会社は買い上げられると一般には考えられた。 仮に一地域に複数の事業社が並列的に設備を構築した場合、 設備の買上げのさいに面倒が起こることが当然予想された。そこで、逓信省は、 原則として一地域一社しか電話局免許を付与しなかった [29]。 しかも、外国資本の全国的企業が市場の大部分を占めるという状態は、 伝統的に独占を嫌うイギリス人の心性に訴えた。とにかく「独占的電話事業者である」 ということ自体が、地域の反発を招いていた。そこで、 免許の事業地域はできるだけ小さく設定された。統一的な事業体が存在するよりも、 バラバラの小さな電話会社が存在した方が、 競争的な市場環境であるとイギリス人たちは考えていたようだ。 規格を統一しないまま操業地域を限定したことは、都市間の通信制限を意味しており、 利用者にこの上ない不便をもたらすことになった。 このため1884年に逓信省は政策を変更し、電話事業免許をうけた事業者は、 総収益の10%の免許料さえ支払うならば、 事業を国内のどこでも任意の規模で行うことができることになった [30]。だが、 1884年の政策変更後ただちに判明したことは、最善の効果をあげようとすれば、 システムの統一性、方式の均一性、 管理運営の集権制および前加入社間の完全な相互通信が欠かせないということであっ た。こうした事情から、民間電話会社の合併がすすむことになり、1889年には、 UTCを母体とした、National Telephone Company (以下「NTC」)が、 イギリス全土へ電話事業を拡大することになった [31]。 地域毎に分割されていた回線を相互に結ぶための基幹回線も必要とされた。 そこでUTC (NTC)は、逓信省に対して幹線網建設の申請をおこなった。 しかし 逓信省は、電信事業の延命を図るため、あらゆる機会をとらえては、 UTC からの要求を先延ばしした。最終的に逓信省は、みずから電話幹線を建設・ 維持することを提案、電話会社には有料で貸与することにした。 電話会社には逓信省の提示した条件を飲む以外の道はなく、 高額な回線賃貸料等の条件を飲むことになる。 [32]。この高額な回線賃貸料のため、 電話会社は、長距離電話事業において赤字による運営を余儀なくされた。 これが長距離通信の抑制と、電話会社への抑制効果を発揮することになる。 逓信省側には長距離通信回線料を合理的に決定するという動機付けも能力も存在して いなかった。 さらに、1891年に逓信省は、 NTCがさまざまな障害を乗り越えて努力のすえに構築していた電話幹線網を国に移管 することを要求する。しかしながら、逓信省には、 電話幹線業務をすべて引受けることができる能力がなかったため、 NTC側に支援を求めた。 逓信省が扱いかねていた電話幹線をNTCが引き続き運用すること、 および同幹線の移管が徐々に進行することに同意が成立した。また、NTCは、 熟練を積んだオペレーターを逓信省に送り、 かつNTCの交換機室で逓信省の職員の訓練を行うことまでも承認したのである [33]。 幹線網の国有化につづいて、地方自治体による自治体電話会社を政府が後押しすべき、 という議論が高まった。民間電話会社の劣悪なサービス、 高額な料金が継続的に批判されてきた影響である。しかし、 それらの不都合の大部分は、消費者に転嫁された、 理不尽な政府の政策から生じるコストに他ならなかった。地方自治体は、 逓信省の支援と、保有する通行地役権を武器に民間電話会社を牽制する一方、 自らは通行地役権を無条件に行使できるため、 短期間のうちに自治体電話事業を展開する。しかしながら、それらの電話事業は、 ハル市(Kingston upon Hull)の事業を除いて、 短期間のうちに失敗するにいたった [34]。 通行地役権(right of way / waylerave)の問題は、 電信時代のはじめから管路の建設にともなう大きな制約であった。電話会社は、 工事を迅速、経済的に実施するための法的権能をまったく欠いていた。 私有地であれば、それぞれの地権者に通行地役権を設定してもらうしかなかった。 もっとも面倒だったのが地方自治体が保有する公有地だった。UTC (NTC) と見るだけでも独占事業者(monopolist)と決めてかかる地方自治体は、 自治体がもつ通行地役権をUTCを牽制するための道具として用いた。 これによってUTCは、事業にさまざまな制約が設定され、 これが通信コストを引き上げる原因となる。 イギリス電話事業の制度的失敗は、免許付与権、 通行地役権のいずれもが公的機関によって握られ、UTC (NTC) を牽制するための手段として用いられたことにある。 電話事業に絶対的に必要なそれらの権利は、 なんらの原則もなく恣意的に公的主体によって行使され、 不合理な制約を電話事業上に設定することになった。免許権、通行地役権の保有者は、 それらの権能を、合理的に行使する動機付けをまったく欠いていた。 私的主体であれば、利益をめざして交渉・妥協する余地もあったのだが、 それら権利を行使する主体には、それらの権益を経済的に用いる必要がなかった。 むしろ、それらの権能は、 UTCを牽制するために政治的に用いられたのであった [35]。
3 放送 初期のラジオ技術は、「無線電話」と呼ばれて研究が進められた。 読んで字のごとくワイヤーのない電話という位置付けである。すると、携帯電話が、 もっとも若いラジオ技術の直系の子孫ということになろうか (もちろん携帯電話は、 もはや無線電話にとどまらないが)。ラジオ機器は、 双方向メディアとして開発が進められた「無線電話」 から送信機能を排除した機械である。 1864年にマックスウェル(James Clerk Maxwell)が電磁波理論を証明し、 電磁波による情報伝達の可能性が指摘されると、 すでに実用化されていた有線電信を無線に置き換える実験が開始された。 1895年にマルコーニがイギリスで無線電信を実用化する。 ただちにモールス信号の無線伝送につづいて音声の伝送が目指された。 このとき画像の伝送についても当然検討されたと思われるが、 研究の方向は音声を中心として進む [36]。 これは、 当時のもっとも巨大な電気技術研究組織が電話会社に帰属していたことが理由であろ うと思われる。アメリカではベルの電話基本特許を基礎に設立されたベル電話会社は、 圧倒的な市場占有力をもって音声通信市場を独占すると同時に、巨大な研究組織、 ベル研究所を所有し、加えて電気通信設備・機器製造会社 WEを支配下に収めていた。 1909年、AT&Tは、無線技術に取り組みはじめ、ド・フォレスト(Lee De Forest) が1906年に発明した三極真空管特許を取得した。無線による情報伝送は、 無線電話の開発の方向に向けられたのである [37]。 1915年には、無線電信を扱っていたAmerican Marconi社のサーノフ(David Sarnoff) によって「Radio Music Box」のアイデアが示されている。彼は、 かつて有線電話で試みられた、有線音楽配信のアイデアを踏まえて、 無線による音楽配信を構想した。彼は、 電波が一斉同報的に情報を伝達することに着目し、家庭に受信専用の無線機を設置し、 そこに音楽や有益なアナウスを同報することを提案した。しかし、 当時のMarconi社の社長は、この着想を「遊び」であると考え却下してしまう。 このことからもこの当時の無線技術が双方向通信に向けられていたことがうかがわれ る [38]。 無線技術は、アメリカにおいては、WE、General Electric (以下「GE」)、 Westinghouse(以下「WH」)などによって開発が進められたが、 それぞれの会社が技術特許を保有し、相互にクロス・ ライセンスしなければ合法に無線機を製造できないという閉塞状況に陥った。 そこで連邦政府の呼びかけで、1917年相互特許協定が結ばれ、 ようやく無線機の大量生産が可能になる [39]。まず、 この特許プールに参加した企業によってのみ無線機が供給されるという法制度的事情 が、その後の技術開発に参加するプレーヤーを限定する機能を果たしたといえよう。 電信電話関連企業が無線技術のプレーヤーとして固定化されたわけである [40]。 第一次世界大戦で無線技術の重要性が認識されると、アメリカにおいても電波 (この当時は「ラジオ技術」と電波の関係は一体として見られていただろう) の国家監理が提唱される。しかし、 AT&Tをはじめとする通信産業界の強硬な反対と、 電信電話時代から継続されてきた「私的企業の自由を最大限尊重しようという、 アメリカが培ってきていた経済民主主義の規範の存在」 [41] によって国家監理案は否定された。 仮にここで欧州諸国や日本のように電波の国家監理が実現していたら、 この当時の通信機器としての無線技術観が長く固定化されることになったことは疑い ない。 電波の国家監理は回避されたが、アメリカ海軍の主導によって、 国策会社RCA (Radio Corporation of America) が設立される。 1919年から21年にかけて、RCAは実質的にGEの子会社となり、 無線技術関係のプレーヤーによって更なる相互特許協定が締結される。この 「1919-21年相互特許協定」によってGEとWHが受信機の独占製造権、 RCAが受信機の独占販売権、AT&TとWEが送信機の独占製造・賃貸・ 販売権をそれぞれ獲得することになる。 この知的財産権を根拠とした閉鎖的産業構造が、 無線通信がラジオ放送へと転換した後、 さらにはテレビ放送にまでをも規定することになる [42]。 無線通信から放送への転換はどのように起こったのだろうか。 1920年頃のアメリカでは無線実験の一環として、 無線マニアが蓄音機で演奏されるレコード音楽をマイクで拾って送信するなどの活動 を開始していた。こうした素人の音声送信実験は、 不定期に行われていたが次第に継続的かつ定期的に送信が行われるようになる。 そのうち、 こうした無線送信が受信機の販売促進手段として有効であると考えられるようになり、 WHが定時送信を事業として開始することを決定する。これが「放送」 の始まりの様子である。また、最初の放送内容は大統領選挙の開票速報であり、 放送内容は新聞を読み上げるという方法で行われた [43]。こうして、KDKA、WBZ、 WJZといった放送局が設立されるようになる。アメリカ以外の諸国では、 放送局の設置が国家主導で行われたのに対して、 アメリカではあくまでも民間事業として開始された。これは、 当時の無線関係法である「1912年無線法」が、 最低限の資格要件のみで無線局免許を付与していたからである。 初期の放送において、放送内容は、SPレコード、 新聞など他のメディアのコンテンツを借用していた。1920年代を通じて、 送信内容全体の約70%を、 音楽が占めていたという [44]。 仮にラジオ放送の黎明期に音楽事業者や新聞事業者が著作権を盾に放送の差止を行っ たら、放送事業の立ち上がりはかなり遅いものとなっただろうし、 放送事業の中心的プレーヤーがレコード業界と出版業界によって占められたかもしれ ない。この時期、音楽著作権を主張する権利者団体が、 ラジオによる音楽の使用を問題視して活動を開始していた事実については注意すべき である [45]。 また、1920年代の半ばまで、正面から広告を放送することは行われなかった。広告を「はしたないもの」と考える雰囲気があったという。このため、ラジオ放送事業は、収益モデルを30年代半ばまで模索しつづけることになる。受信者を特定することが困難な放送における収益モデルの模索は長く続けられたし、 様々な方法が提案され、 実験された [46]。 単なる放送実験ではなく、聴くべき内容を伴った放送が開始された当時、 受信者のほとんどは、送信能力をもっていた無線技師、あるいはその予備軍であった。 しかし、KDKAが定時放送を開始したことで、単に通信内容を受信するだけの「聴衆」 が形成されるようになる。こうした受動的な「聴衆」が増加していくことを、 古くからの無線技師たちは無線技術の堕落と感じたという [47]。しかしながら、 機能を受信に限定したことで扱いやすい「商品」として完成されたラジオは、 大恐慌による不況にもかかわらず急速に家庭に普及し、 1940年には80%を超える普及率に達した [48]。初期のラジオは、リビング・ ルームに設置することを目的として、木製家具、調度品、 蓄音機のデザインを踏襲した。音の出る「家具」として社会に受容された。
3.1 通信と放送の分離1919-21年相互特許協定の一角を占めていた通信事業社AT&Tは、 放送事業に対してどのような態度を示したか。ラジオ放送が開始された当時、 AT&T社内には、ラジオ事業を推進すべきとする無線派と、有線電話事業を堅持し、 音声コンテンツ配信を電話線を通じて行うべきとする有線派にわかれて議論が続いて いたという。やがてAT&Tは、ラジオ放送を、 電話線と無線を組み合わせて行われる 1対N (あるいは「1対多」) の有料広報電話というようなサービスであると理解したようだ。AT&Tは、 情報内容を制作せず、あらかじめ契約を交わした者に対して、 聴衆に音声を伝達する手段を有料で提供するサービスを運営する [49]。まさにコモン・ キャリアとしての事業を構想していたのである。このシステムは、 Public Address System (以下「PAS」)と呼ばれた。ラジオ放送が公衆電話事業の一種であれば、 それはAT&Tが政府の規制下に容認された独占領域であることになる。当然、 AT&Tは、 無線サービスを無線電話の枠内に収まるものとして確立しようとつとめた [50]。また、長距離電話回線と、 長距離伝送技術に長けたAT&Tは、 アメリカ各地の放送局を有線でネットワークするようになる。 電話事業でAT&Tが勝ち残った理由は、 まさに基幹ネットワークを制覇したことにあった。もし、同じ戦術が使えたなら、 AT&Tは、無線領域においても独占的支配力を発揮するようになっただろう。 ところが、AT&Tは結果的に無線事業から撤退してしまうことになる。むしろ、 有線電話事業にみずからの活動領域を制限せざるえない立場におかれてしまう。 まず、PASの顧客は、メッセージを伝達したいと考える人物ではなく、 広告をひろく伝達したい諸企業だった。電話と異なり、目的とした人物だけでなく、 電波の到達する領域全体にメッセージをばら撒く無線通信は、 広告がもっとも適した用途だったからである。しかし、 広告だけを流しつづけるのでは、PASの聴衆はいなくなってしまう。 そこで広告を聴いてもらうだけの価値のある「内容」 を準備しなければならなくなった。 ここで電話事業とは異なる事業が必要とされること、また、 その事業をAT&Tが遂行できないことが認識されることになる [51]。 次に、独占禁止法の影響である。1919-21年相互特許協定で、AT&Tは、 放送用送信機の製造販売権、(無線放送を電話事業だと定義することで) 有料放送を行う権利、放送ネットワークの所有権を独占するものと主張してた。 このため、 他の協定参加企業が放送事業の収益モデルを構築できず呻吟していたのに対して、 AT&Tは、 着実に放送事業から収益を上げていた [52]。 ちょうどこの頃から連邦通商委員会(Federal Trade Comission、以下「FTC」)は、 RCAを中心としたラジオ産業についての独占禁止法違反の疑いで調査を開始していた。 1924年には、RCA関連7企業について独占禁止法違反の疑いが強いとの勧告が行われた。 RCAの独占に対する社会的反感が高まっていた [53]。関係企業は、 ラジオ事業への独占禁止法の適用によって本業に損害が及ぶことを恐れた。そこで、 AT&TはRCAの株式売却、所有放送局の売却、放送送信機の製造・賃貸・ 販売独占権の放棄などを通じて、AT&Tが放送事業から撤退し、 放送ネットワーク事業に専念する立場を選択した [54]。 AT&Tの放送事業からの撤退は、「1926年相互特許協定」として固定化される。 この特許協定の枠組みと、後のAT&T独占禁止訴訟が組み合わさることで、 AT&Tは、有線音声通信の枠内にみずからを封じ込めることになる。 これが理由となって、画像伝送は、 放送という枠組みの中に位置付けられることになったのだ [55]。 1926年特許相互協定の結果、 RCAの放送事業部門の子会社としてNBC (National Broadcasting Company) が設立される。これによって現在の「放送」 事業の形態的枠組みが確定するのである [56]。また、 より質の高い放送番組製作に必要な資金の高騰が、 財政基盤の弱小な小規模の事業主体を放送から排除することになった [57]一方、 新聞社によるラジオ放送事業への進出がすすんだ。1933年には、 13.4%の放送局が新聞社による経営だった [58]。こうして、 何らかの政府による対策が行われない限り、放送事業は、 広告を収益源とする事業モデルを採用するようになる。そしてテレビ放送以降、 それがあたりまえのことのようになっていくのである。
3.2 制度的枠組みの固定1934年通信法(Communications Act of 1934)によって、 情報通信を専門的に監理する独立行政委員会 連邦通信委員会 (Federal Communications Commission、以下「FCC」)が設立された。1934年通信法は、 その当時の情報流通環境を前提にして、通信事業規制を基本に置き、 放送事業を通信事業の一種として取り扱っていた。この構造は、 当然にFCCの内部構造にも反映し、 通信と放送の二大枠組みは制度的に固定されることになる。これが現在まで続く、 通信と放送の二大枠組みを所与とする法的・制度的思考枠組みを形作ることになる。 FCCが規制する対象とは、1970年代末までについては、 要するに巨大通信事業体 AT&Tと、 巨大放送産業体 RCA / NBC (National Broadcasting Company)/ CBS (Columbia Broadcasting System)であり、様々な反独占禁止法訴訟や行政的な対応は、 その当時確立していてた通信・ 放送の二大勢力への公共的観点からの介入という性格をもっていた。それゆえ、 FCC規制が積み上げてきた法理論、判例は、 それらの二大産業の枠組みを所与の前提としているのである。1920年代頃においては、実質的に放送事業は存在せず、通信事業は 州際通商委員会 (Interstate Commerce Commission、以下「ICC」) によって規制されるものとされていた。これは、1910年マン・エルキンズ法 (Mann-Elkins Act)によって、 それまでもっぱら州際鉄道輸送事業を規制してきたICCに、州際通信事業規制 (州際及び外国通信を行う一切の有線及び無線の電信・電話、 さらには海底ケーブル路線)をも担当させることが決定されたからである。 通信を輸送事業の一種として把握する1910年当時の考え方が反映したものであるとい えよう。しかし、 ICCのこれらの事業会社に対する規制はそれほど厳密なものではなく、 またICCの中には通信問題のみを専門に扱う特別の部門・局・課は設けられず、 実際には鉄道問題を監督するために設立された既存の組織を通じてなされたのであっ た。[59] 後に放送部門については、 1927年無線法(Radio Act of 1927)に基づいて、 連邦無線委員会 (Federal Radio Commission、以下「FRC」)が設立された。 1927年無線法では、無線電波が公衆の物であるという観念が示され、 電波周波数のFRCによる監理が制度化された。しかしながらFRCは弱体な組織であり、 大資本によって運営される放送ネットワークを十分に制御することができなかった。 とくに、1927年無線法において、放送ネットワーク技術(事業形態)が、 放送産業を支配する鍵となる事業形態であることへの認識が欠けていたとされる。 しかし、このことによって、NBCやCBSなどの放送ネットワークは、 産業として最大級の発展を遂げることが可能になった [60]と評価されている。 ICCにしても、FRCにしても、新技術が新産業として確立し、 市場支配力を過剰に発揮するようになるまで積極的な規制を行わなかった。 自由放任主義のアメリカ風土が産業の発展には よい方向に作用したのであろう。 効率的な事業形態は、規制当局が決定するものではなく、 事業者による努力によって探求されるものだからである。 ICCとFRCがこれといった対処をしない期間、 さまざまな事業者によって様々な事業形態が実験された。 その結果として登場したAT&TとRCAによって通信・ 放送事業形態は完成をみたのである。電話事業の揺籃期に過剰な介入を続けた結果、 新産業を窒息させてしまったイギリス政府の事例とは対照的である。 上記の状況からわかるように、制度的枠組みとは、 制度が構築された時代における一時的な事業の状態を反映したものであり、 日々変化を続ける技術や社会状況を、制度的枠組みに組み入れようとすることは、 とくに柔軟性をもつ新技術にとっては致命的な悪影響を及ぼす危険がある。 現在のコンピュータ・ネットワークを利用した情報伝達を、単純に「通信」 の枠内に収めるのは賢明ではないだろう。今、必要なのは規制緩和(水平分離) による情報通信環境の再構築を促進する政策である。おそらく10年ほどすれば、 コンピュータ・ ネットワーク時代に適合した事業形態をもった事業者が市場支配力を発揮するように なるであろう。その時に、 その事業形態に適合した規制枠を設計することが必要となるのである。
3.3 テレビ放送テレビ放送、すなわち地上波テレビ放送は、第二次世界大戦後に一般化した。 私たちは、その当時の一般的な形態であった箱状の機器を「テレビ」と認識する。 それは、電波によって送られてきた音声・画像情報に同調し、 ブラウン管スクリーンに動画を表示し音声を同期して再生する機器である。 このテレビ形態は、それ以前のメディアであるラジオからの発展的類推であり、 実際にごく初期のテレビ受像機は、 その当時のラジオの周波数表示窓をブラウン管に置き換えたデザインを採用していた [61]。また、 テレビ放送は当然にラジオ放送の制度枠、規制枠を継承するものと考えられたし、 その事業は(ラジオ)放送事業者が発展的に行うものと認識された。しかし、このテレビ観は、現在コンピュータやビデオゲーム等の発展により、 ディスプレイ装置 + オーディオ装置 + テレビ放送チューナー の複合体であること が認識され、現在、コンピュータとの活発な融合を進める一方、 それら三要素を組み替える試みが進んでいる。 テレビ放送分野における通信と放送の融合とは、「テレビ放送チューナー」の部分が、 他の伝達手段に置き換わるプロセスだと見ることもできる。すなわち、 私たちのテレビ観というものは、ある一時的な安定形態を前提にした物である。 「テレビ」という枠を離れ、画像伝送という観点でみれば、 それは電話よりも古い歴史をもつ。1863年にアメリカで特許が付与された 「パンテレグラフ」 という電信技術を応用したファクシミリ類似の機器が画像伝送技術の最初であるとい われる。このパンテレグラフでは、画像を電気信号に変換するために、 導電性の特殊なインクを用いて描かれた画像のみを送ることができた。1891年には、 セレンを光電素子として用いることで、 一般的な画像を電気信号に変換することに成功し、 有線による画像伝送の実用化に貢献した。そして、 20世紀の初頭にはすでに有線による画像伝送が商業化され、 新聞産業における写真の伝送などに用いられていた [62]。 また、私たちは、電波を用いた画像伝送が、 ラジオ放送の実用化をうけて研究されはじめたと思いがちだが、実際には、 電波による音声伝送と同時期から研究が開始されていた。水越 氏は、 ラジオ放送という産業が急速に発展する中で、 テレビ研究がむしろ後回しにされたことを指摘している。 テレビが実用化されていく中で、テレビは、 ラジオ放送事業という形態に意識的に揃えられたのである [63]。 従って、テレビ放送が無線伝送を前提としなければならない理由も、また、 電波による伝達という本質的制約から派生する一斉同報伝達の必然性もなかったので ある。事実、きわめて初期の画像伝送のアイデアのなかで、テレビは、 電話と映画を組み合わせたようなものとしても構想されていた。画像伝送には、 初期の段階から通信を基礎とした双方向メディアの可能性もあったわけだ [64]。 ではなぜ、テレビはラジオ放送の発展形として位置付けられたのか。経済的・ 制度的理由が存在する。水越氏は、三つの要因を挙げている。(1) 第一次世界大戦におけるラジオ無線電信への国策的な研究開発の集中、(2) 戦後 (第一次世界大戦)ラジオがマス・メディアへと変転し、 人々の生活のなかに急激に普及したこと、(3) 大恐慌によるラジオの産業的確立と、 1930年代のマス・メディアとしての(ラジオの)隆盛がテレビジョンを疎外したこと、 である [65]。 技術的に比較的複雑なテレビ開発がラジオ開発に遅れることは当然として、 いったんラジオ技術が実用段階に入ると、 研究開発がラジオ技術改良に集中することになる。 これをうけてラジオ産業が離陸すると、 ラジオが媒体として用いる電波のもつ一斉同報性から「放送」 という事業形式が確立し、放送局や伝送ネットワークなどが完備されるようになる。 つまり、無線伝送に関してのインフラが整備されるわけで、 画像を無線で伝送するための基礎条件が整うことになる。 ラジオが事業が成功を収め大産業として成立すると、 テレビ開発競争に投入できる資源の面において圧倒的に有利となる。 するとテレビ開発においてラジオ事業者が有利となり、 必然的にラジオ事業に用いられたインフラを活用する方向にテレビの形態が揃えられ ることになる。当然、テレビ開発の初期段階から有線(電話線) による画像伝送が可能であったわけだが、そのように歴史が展開しなかったのは、 1926年特許相互協定以降になされた幾度かの独占禁止法訴訟の結果、 電話会社が放送事業へ進出できないように制約されていたことが理由である [66]。 また、ソフトウェア面からみれば、チャンネルを時間軸で編成していく「番組概念」 がラジオからそのままテレビに継承された。しかしながら放送業界は、 映像ソフト制作のノウハウをまったく持っていなかった。そこで、 テレビ番組制作の多くは、 映像ソフト制作企業であった映画産業に依存することになる [67]。アメリカの放送事業は、 ハリウッドとの強い結びつきをもち、すでに1930年代にはハリウッドは「映画の都」 にとどまらず、総合的なメディア産業の中枢機構として成立していたという。 私たちがハリウッドを「映画の都」と認識するのは 「ハリウッド自身が反独占の世論や法律をかわすために身に付けてきた、 巧妙な自己規定、自己PRの所産だった」 という [68]。
Note
|

 | 白田 秀彰 (Shirata Hideaki) 法政大学 社会学部 助教授 (Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences) 法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450) e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp |